|
| |
|
| |
北里大学 江川 徹
(高等教育開発センター FD推進部門長)
「授業公開の憂鬱」
今回のエッセイは,全学的な活動内容についてではなく,一般教育部での授業改善についての話である。
本学一般教育部でも,ご多分に漏れず教員相互の「授業公開・授業参観」を行っている。前期と後期それぞれ1回,2週間ずつを「授業公開週間」として,公開してくれる授業を事前に募る。それを一覧にして所属全教員に配る。各教員はそれを見て興味のある授業を参観する。いかにして「強制せずに参加者を増やすか」を考え,なるべく面倒な義務を課さずに参加への敷居を低くしようとした結果,授業の公開も参観も,完全に任意にし,参観の事前通告も参観後のレポートも課さないことにしている。参観した授業の中で参考になる点があれば,各自がそれぞれの授業で反映させればそれで良い。
それでも,授業公開・授業参観ともに参加者は増えない。まず,授業を公開する教員の顔ぶれが固定されてしまい,その結果,公開する授業の中身も毎年あまり変わらなくなってしまった。それにつれて参観の参加者が減ってしまったというのが現状である。どうも敷居を低くするだけでは不十分のようである。
そもそも「授業公開・参観」の目的は何かというと,いわゆる「教員による相互評価」ということを除き,「授業改善」に目的を限定して考えると
①参観者が公開者の授業の良い点を参考にして自分の授業に役立てる
②公開者が参観者に授業を批評してもらい自分の授業を改善する,
の2点になろう。このうちの①を強調したのが授業を公開する教員が増えない理由と思われる。「授業を見せてもらい,お手本にする」という面を強調すると,授業を公開する教員は自分の授業を「他の手本になるもの」と認識しているということになる。「私はそこまで思い上がってはいない」という教員は,授業公開への参加を遠慮する。
それなら逆に②の「授業を批評してもらい改善の参考にする」という面を強調すれば良いかというと,今度は授業を参観する教員が減ると思われる。「私は自分を,他の教員の授業を批評できるほど偉い人間と思ってはいない」という訳である。もちろんこれに加えて「自分の授業を他の教員に批判されるのは嫌だ」という心理も働く。
「だから参加を強制的に割り当ててしまえば良いのだ」という意見も一部の教員にはあるが,嫌々やらされるFDというものにどれだけ意味があろう。とは言うものの,もう少し参加者が増えてくれないものかと,悩みは尽きない。
|
| |
|
| |
Copyright 2009 Yamagata University higher education research project center , All Rights Reserved. |
|
| |
|
このホームページに関するご意見・お問い合せは、山形大学高等教育研究企画センターまで。
山形大学 高等教育研究企画センター 〒990-8560 山形市小白川町一丁目4-12
TEL:023-628-4707 FAX:023-628-4720 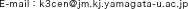 |
|
|