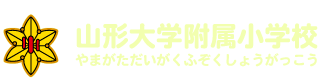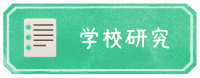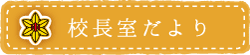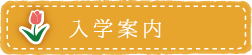わたしたちの取り組み2024
1 わたしたちの子ども観と目指していること
わたしたちは、これまでの研究を通して、「子どもは、事象(人・もの・こと)との関係の中でよりよい自分になりたいという思いや願いをもっている」と捉え、子どもの学びを洞察し、働きかけてきた。子どもの学びを洞察するとは、子どもの具体的な姿をもとに、少しでも子どもの内面に近付き、子ども理解を深めることである。また、これまでのその子どもの学びをもとに、これからの学びの可能性について見通しをもつことである。
子どもは、事象との関係の中で、思いや願いをもち、それを実現させる過程で出合う問題を様々な方法で解決しようとする。そして、事象に対する自分のとらえを更新していく。わたしたちは、このような子どもの歩みを「子どもの問題解決」と呼び、よりよい自分に向かうために必要なことであると捉え、大切にしてきた。
わたしたちが望んでいるのは、子どもが自ら問題解決を進めていくことができるようになることである。事象と出合った時に、自身の思いや願いに応じて様々に見方・考え方を働かせて事象に関わり、自ら問題解決を進める子どもを育てたい。そのような子どもが、持続可能な社会の創り手として、これからの時代を豊かに生きていくことになると考えている。そこで、わたしたちは、2022年度から次の研究主題を掲げている。
子どもは、事象との関係の中で、思いや願いをもち、それを実現させる過程で出合う問題を様々な方法で解決しようとする。そして、事象に対する自分のとらえを更新していく。わたしたちは、このような子どもの歩みを「子どもの問題解決」と呼び、よりよい自分に向かうために必要なことであると捉え、大切にしてきた。
わたしたちが望んでいるのは、子どもが自ら問題解決を進めていくことができるようになることである。事象と出合った時に、自身の思いや願いに応じて様々に見方・考え方を働かせて事象に関わり、自ら問題解決を進める子どもを育てたい。そのような子どもが、持続可能な社会の創り手として、これからの時代を豊かに生きていくことになると考えている。そこで、わたしたちは、2022年度から次の研究主題を掲げている。
自ら問題解決を進める子ども
わたしたちが考える「自ら問題解決を進める子ども」が身に付けている資質・能力については、「令和6年度山形大学附属小学校資質・能力系統表」(以下、資質・能力系統表)に整理している。
2 わたしたちの取り組み2023から見えてきたこと
(1)育みたい資質・能力と目の前の子どもの姿を往還しながら見つめていくことの価値
わたしたちは、資質・能力系統表をもとに、昨年度一年間の取り組みによって子どもがどのように育ったのか、どのようなところに課題があるのかについて子どもの洞察に基づく話し合いを行った。
全職員で育みたい資質・能力が共有されているため、子どもの育ちを話し合う際に同じ土台に立って話し合うことができた。そこから、教師の働きかけとして重視しなければいけない点なども話し合うことができた。
次年度につなげたいこととして、次のことが上げられた。
全職員で育みたい資質・能力が共有されているため、子どもの育ちを話し合う際に同じ土台に立って話し合うことができた。そこから、教師の働きかけとして重視しなければいけない点なども話し合うことができた。
次年度につなげたいこととして、次のことが上げられた。
〈「知識・技能」について〉
- 子どもが、日々のくらしや遊びの経験からなんとなく知っていることを学びにつなげられるような働きかけをしたい。
- 自分の考えや思いを伝える方法を子ども自身が選択できるようにするには、一つ一つの技能を高める必要がある。同時に、まとめたり綴ったりするよさを感じられるようにしていく必要がある。
- 子どもに必要なのは、根拠と理由を使い分ける力ではなく、根拠や理由を明らかにして自分の考えを主張する力なのではないか。
- 単元や授業で子どもが繰り返し試行錯誤できるような場と時間の設定は欠かすことができず、その時間があるからこそ、子どもが見付けたこと・分かったことから「なんでだろう」という新たな問いが生まれてくる。
- 学習活動の目的(解決したい理由)が子どもの中で明確になっていると、問題解決を進めていくことができる。
- 活動の中で学ぶたのしみを見いだし、自分を客観的に見る目を育てることで自己の変容をさらに自覚できるようにしたい。
- 思っていることがあっても、表現できない姿があるのは、正解ではなかったら嫌だという気持ちの表れなのか。それとも、これまで何も言わなくとも周りがなんとかしてくれたという経験から他人事に感じてしまっているのかを考えていきたい。
- 自分の考えはよく話すが、論理的に書いて伝える力をもっと育てる必要がある。また、授業の振り返りを書くよさを子どもと共有することができているだろうか。
- 子どもは思いや願いをもって取り組んでいるからこそ話したくなる。はじめから話している相手の話に興味をもつとは限らず、聞いてよかった、聞いてもらってよかったという経験を重ねることを大切にしたい。
- 成功しないとゴールではないという、子どもの意識を変えていかなければいけない。失敗することで学べることがあるという前向きな気持ちを育てたい。
- 問題解決の中で、目的・場面・相手などにもう一歩踏み込むエネルギーがほしい。そのためには、自己肯定感、自己有用感が必要になるのだろう。
このように、資質・能力系統表に照らし合わせて子どもの日々の姿を洞察することで、子どもにさらに育みたい資質・能力は何かが少しずつ明らかになり、教師の働きかけを問い直すこともできた。これが育みたい資質・能力と目の前の子どもの姿を往還しながら見つめていくことの価値だと考えている。
これらを基に検討を進め、わたしたちは、令和6年度の資質・能力系統表を策定した。令和6年度は、各教科・領域の実践や様々な行事、日々のくらしなど、教育活動全体で、系統表に示すどの資質・能力を育んでいくのかを明確にしていきたい。また、これらの教育活動を終えた後、実際には子どもにどのような資質・能力がどの程度育まれたのかについても丁寧に振り返りたい。これがわたしたちの働きかけの質を高め、子どもたちの資質・能力を高めることにつながると考えている。
(2)子どもの問題解決における見方・考え方ととらえの更新(概念形成)について
これらを基に検討を進め、わたしたちは、令和6年度の資質・能力系統表を策定した。令和6年度は、各教科・領域の実践や様々な行事、日々のくらしなど、教育活動全体で、系統表に示すどの資質・能力を育んでいくのかを明確にしていきたい。また、これらの教育活動を終えた後、実際には子どもにどのような資質・能力がどの程度育まれたのかについても丁寧に振り返りたい。これがわたしたちの働きかけの質を高め、子どもたちの資質・能力を高めることにつながると考えている。
わたしたちは、子どもが見方・考え方を働かせて学ぶことは、各教科等を学ぶ本質的な意義に向かっていくことだと考えて実践に取り組んできた。継続した取り組みにより、各教科・領域における見方・考え方とは何か、それを働かせることでどのようにとらえの更新(概念形成)をすることができるのかについては、教科・領域部ごとに成果が現われてきている。本誌の「各教科・領域実践編」には、子どもが見方・考え方を働かせて学び、その歩みに合わせて単元を構成していったわたしたちの実践がある。このような日々の授業における地道な積み重ねが、子どもが各教科等を学ぶ本質的な意義に向かう問題解決を進めることとそれを支える教師集団を育てることになると考えている。
今年度も多くの実践に取り組んだ中で課題として出されたことは、子どもが本当に「自ら」問題解決を進めているのかという点である。子どもは確かに見方・考え方を働かせて問題解決を進め、とらえの更新(概念形成)を行うことができているとわたしたちは捉えている。しかし、教師の想定している問題解決の過程を受け身になって取り組んでいる子どももいるのではないか。わたしたちは、これまで以上に子どもが「自ら」力強く問題解決を進めるための働きかけを吟味する必要があると考えた。詳しくは次の(3)で述べる。
(3)子どもが「自ら」問題解決を進めたくなる環境を整え、「自ら」を引き出す働きかけができているか
今年度も多くの実践に取り組んだ中で課題として出されたことは、子どもが本当に「自ら」問題解決を進めているのかという点である。子どもは確かに見方・考え方を働かせて問題解決を進め、とらえの更新(概念形成)を行うことができているとわたしたちは捉えている。しかし、教師の想定している問題解決の過程を受け身になって取り組んでいる子どももいるのではないか。わたしたちは、これまで以上に子どもが「自ら」力強く問題解決を進めるための働きかけを吟味する必要があると考えた。詳しくは次の(3)で述べる。
昨年度、異学年でつくる学びの時間「みのりの時間」を初めて実施した。その中で6年生の班長、5年生の副班長を中心に自分たちで内容を決め、計画を立てて学習に取り組む姿が見られた。調理をする班、理科実験に臨む班、手作りのカードを用いて学校探検をする班など、子どもたちは様々な活動を創り上げていった。そのときの子どもたちの表情は生き生きとしていて、「自ら」問題解決を進める姿そのものだと捉えた。
わたしたちは、なぜこの子はそれに夢中になっているのか、なぜこれにこだわっているのかということをていねいに洞察することで、子どもが「自ら」問題解決を進めるときに必要な鍵となるもの、また、それを支える教師の働きかけの鍵となるものが見えてくると考えた。そこで、わたしたちは、子どもがより力強く「自ら」問題解決を進めることができるようになるために、以下のようなことを考えた。
わたしたちは、なぜこの子はそれに夢中になっているのか、なぜこれにこだわっているのかということをていねいに洞察することで、子どもが「自ら」問題解決を進めるときに必要な鍵となるもの、また、それを支える教師の働きかけの鍵となるものが見えてくると考えた。そこで、わたしたちは、子どもがより力強く「自ら」問題解決を進めることができるようになるために、以下のようなことを考えた。
- 子どもが、自由度と遊び心をもって事象に十分に関わる時間を保障することができているか。子どもが身近に感じ、思いや願いを膨らませていくことができるような環境をつくる必要があるのではないか。
- 友達と関わって学習を進める中で、それをやりたいと思えることも「自ら」問題解決に踏み出した姿である。そうした自分の思いや願いに気付けるよう働きかけをすることもわたしたちの役割である。
- 子どもの遊びの中から学びにつながるものが出てくることが多い。その瞬間を見逃さない教師の洞察力を鍛える必要がある。
- 自由度というのは何でもありの自由ではなく、事象との関わりを生みだす環境の中での自由度である。この環境をどうつくるかは単元の目標と単元計画などの教師の意図と大きく関わってくる。
- 子ども発のものだけでなく、教師が出合わせたものであっても、それが子どものものになっていけばよいのではないか。
- どの学習でも、子どもが自分で選択したりつくったりする場が、「自ら」を生み出すきっかけになる。
- 子どもが時間をかけて、自分が仲間と解決したいと思える課題を立ち上げられているか問い直したい。
- 子どもが夢中になって学ぶきっかけやタイミングは人それぞれである。その子を洞察し、その子の心をくすぐる働きかけを考えられているだろうか。
- 授業の振り返りから子どもの思考を洞察することに加え、授業中の子どもの事実(行動・言葉・表情・友達との関わり)を洞察するこちらの能力を高める必要がある。
- 子どもに問題解決を急がせない単元計画を立てていきたい。子どもが自ら問題解決を進めて、とらえを更新するには多くの時間を有することを心がけたい。
わたしたちが日々の実践を振り返り感じたことを基に、2024年度は、子どもが「自ら」問題解決を進めるために大切にしていきたいことを考えていきたい。
3 わたしたちの取り組み2024で大切にしたいこと
(1)育みたい資質・能力と目の前の子どもの姿を往還しながら見つめていくこと
わたしたちは昨年度の取り組みで見られた子どもの姿をもとに、「令和6年度資質・能力系統表」を策定した。これを土台に、今年度の学級カリキュラムの作成と運用、教科・領域の単元構想、各種学校行事等を進めていく。そして、子どもの問題解決を進める姿を、年間を通して洞察し、全職員で子どもの育ちや課題について語り合うことを大切にしていく。
今年度も昨年度に引き続き、子どもの洞察に基づく話し合いを定期的に行っていく。全職員で、子どもに育みたい資質・能力を共有し、子どもの育ちを話し合う際に同じ土台に立って話し合っていく。そこから、教師の働きかけとして重視しなければいけない点なども話し合い、この取り組みの質を上げていきたいと考えている。
(2)子どもが自ら問題解決を進めるための働きかけを吟味する
今年度も昨年度に引き続き、子どもの洞察に基づく話し合いを定期的に行っていく。全職員で、子どもに育みたい資質・能力を共有し、子どもの育ちを話し合う際に同じ土台に立って話し合っていく。そこから、教師の働きかけとして重視しなければいけない点なども話し合い、この取り組みの質を上げていきたいと考えている。
わたしたちは昨年度の取り組みから、子どもは「自ら」問題解決を進めることができているか問い直し始めた。ここでいう「自ら」とは、子どもが事象と関わる中でもった思いや願いを出発点に、自らの見方・考え方を働かせて事象に関わることに夢中になっていることだ。子どもが自ら問題解決を進めるからこそ、子ども自身の力で事象のとらえ(概念)をより高次なものへと更新させることができ、そこに学ぶ価値を見いだしていくことになると考えている。
昨年の議論の中で、「自ら」問題解決を進める子どもの育ちを支えるために必要ないくつかの視点が出された。〔2の(3)を参照〕これらを整理した結果、わたしたちが今年度の実践をつくっていくときには、常に次の3つのことに立ち返り、自分に問い直していきたいと考えている。
昨年の議論の中で、「自ら」問題解決を進める子どもの育ちを支えるために必要ないくつかの視点が出された。〔2の(3)を参照〕これらを整理した結果、わたしたちが今年度の実践をつくっていくときには、常に次の3つのことに立ち返り、自分に問い直していきたいと考えている。
子どもに教科・領域の特質に応じた自由度のある学びの環境をつくること。
- 事象(人・もの・こと)に十分に関わる単元を構想できているか。
- 自分たちで選択したり決めたりする場があるか。
- 子どもに問題解決を急がせていないか。等
- 子どもがこれまでにどのような経験を積み重ねてきているのか。
- 子どもが、事象(人・もの・こと)に出合い、どのような見方・考え方を働かせているのか。
- なぜこの子は夢中になっているのか、なぜこだわっているのか等を、行動・言動・表情・友達との関わりからどのように考えることができるか。
- 子どもが、現在のとらえをどのように更新していくことができると考えているか。等
- 子どもが、その単元で鍛え、より働かせてほしい見方・考え方、また、目指したいとらえの更新(概念形成)について言い抜けているか。
- その教科・領域の本質に向かうために、子どもの心をくすぐる問いをわたしたちが設定できているか。等
この3つのことを常に自分に問い返しながら、自ら問題解決を進める子どもを育てることを目指していきたい。