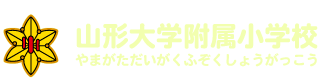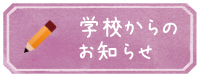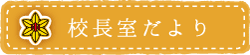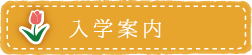校長室だより
全校朝会での校長講話②(参集型)
「品」を導く「ほっとの種」
令和7年7月2日 校長 早坂 和重
みなさん、おはようございます。
今日の千歳山は青い空にくっきり浮かんでいます。初夏の装いです。夏の元気な附属小のみなさんのお顔のようです。前回の全校朝会は5月8日でした。約2か月の間に、開校記念式、大テーマ発表、みのり班清掃開始、公開研、みのり遠足などなど、たくさんのことがありました。
ところで、みなさんは、5月8日の朝会の話を覚えているでしょうか。もしそんな前の話を覚えていたら、とてもすごいことです。さあ、何だったでしょうか。…答えは「品について」でした。「品とは、サトシさんにとってのポケモンマスターのように求め続けるものではないか」ということ、そして「品は、自分で自分をコントロールすることで、少しずつ身に付くのではないか」という話でした。こんなふうに、時々、振り返るということも、自分の学びをたしかにするときにはとても大切だと言われています。逆に考えれば、何かを振り返って考えてみることがなければ、あまり学べないのかもしれません。この全校朝会のように、みんなで集まる場(学年集会なども)を、一人一人が振り返って考える場としてみてはどうでしょうか。
さて「考える」というと、ちょっと難しいような感じがするかもしれません。でも、安心してください。約100年前の哲学者(デューイ)さんは、思考の本質についてこんなことを言っています。
「私が思考する」(I think.)というよりは、
まるで「雨が降る」(It rains.)と同じように、
「思考がなされる」(It thinks.)
この言葉によれば、考えるということは本質的には、雨が降るのと同じように、自動的になされるということです。たしかに、生きていれば、何も考えないということの方が難しく、いつも何かが心に浮かんだり消えたりしているのではないでしょうか。
ただ、考えるということが自動的であるとしたら、それは自動的であるがゆえに、自分ではコントロールできないということも含んでいます。ただ、私が毎日みなさんと一緒に学校でくらしていて、このことについて、今、はっきりと言えることがあります。それは、何かに本気で、自分で自分をコントロールすることも忘れ、夢中になって一生懸命取り組んでいるみなさんの姿には「品」を感じるということです。つまり、大テーマの「3つの種」の一つ目「ほっとな」が、「品」につながるのではないかということです。前は「自分で自分をコントロールすること」で「品」が身に付いていくということを思っていたのですが、どうもその逆もありそうです。
ここまで考えて思ったことについて言葉を変えてまとめてみます。夏ですね。バーベキューの炭を知っていますか。炭火は水をかけても簡単には消えません。ああいった簡単には消えない、熱く燃え続けるほっとな「問い」を抱えた学びには、振り返って考えた時に、何か一貫したストーリーが出てくるのではないか。また、そのような学びが、自分の人としての成長を促し、みなさん一人一人に「品」を導いてくれるのではないかということです。
最後にお聞きします。今、みなさん一人一人は、何について心がほっとになっているでしょうか。「ちょっとおもしろそう」「やってみたい」という「好奇心」も学びの始まりです。ぜひ、振り返って考えてみてください。そして、その「ほっとの種」を夏休み中も大事に育てることができるよう願っています。次回の朝会は、また約2か月後の9月12日です。また全員で元気にお会いできればと思います。以上でお話を終わります。