


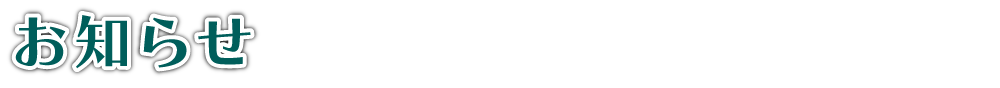



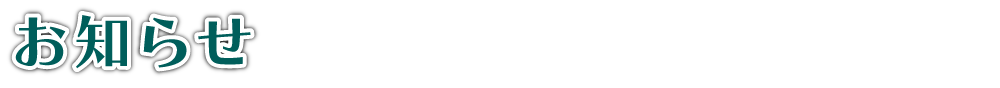
ホーム > 新着情報:お知らせ > 2024年07月 > 国立大学協会声明に関する学長所感 「高等教育の在り方について、いま議論すべきこと」
掲載日:2024.07.04
山形大学は、今年で創立75周年となります。昭和・平成・令和の時代を通じて、10万人を超える有為の人材を世に送り、社会の発展に貢献してきました。現在も、本学が掲げる3つの基本使命「地域創生」、「次世代形成」、「多文化共生」の実現に向けた教育、研究、社会共創を推進し、地域人材育成と新たな地域価値の創出に取り組んでいます。
しかし、先般、国立大学協会が発表した声明(令和6年6月7日)にもあるように、国立大学を取り巻く財務状況は非常に厳しくなっています。物価や光熱費、人件費が増加する一方で、運営費交付金の基幹的経費は段階的に削減されています。各大学では新たな財源を確保するために、外部資金の増加や固定資産の有効活用等に努めていますが、これらの取り組みは地域経済の規模に左右されるため、地方の大学は大都市圏に比べてさらに厳しい状況に直面しています。
このような厳しい財務状況の中、国立大学の授業料の引き上げについての議論が社会で注目を集めています。しかし、その議論において、地域格差への視点が欠けているのではないかと感じることがあります。
大学進学率には地域差があり、東京都では大学進学率が70%を超える一方、山形県など東北各県では40%台にとどまっています。これは、大都市圏と地方での所得格差や、大学入学前の教育機会の格差が影響していると考えられます。また、地方都市では自宅から通える大学が少ないことも、大学進学率の地域差を生む要因となっています。
高等教育に関して、このような地域格差がある中で、受益者負担で教育の質を高めるとする競争主義的な考えが社会で広まることには大きな危機感を覚えます。
高等教育の在り方について、いま社会全体で真っ先に議論すべきなのは、授業料の引き上げではなく、教育の機会均等に向けた公費の拡大です。特に、所得格差に対しては奨学金制度の拡充、地域格差に対しては人口減少地域の教育を支える国公私立大学や専修学校への一層の財政的支援が、議論されるべきです。
人口減少が喫緊の課題である山形県において、山形大学には県内外から若者が集い、キャンパスでの学びと生活を通じて地域に大きな活力をもたらしています。山形大学は、地域を支える多様な人材の育成、産学官金連携による新たな地域価値の創出、医学部附属病院と東日本重粒子センターによる地域医療への貢献などを通じて、地域社会の発展にますます力を発揮していきたいと考えています。また、本学が創設したやまがた社会共創プラットフォームを通じて、県内公私立大学との連携をさらに深め、地域の高等教育を支える共通基盤としての役割を積極的に果たしてまいります。これからも、山形大学と社会の皆様が、経済、文化や生活の充実・向上において、多様で多くの関わりを持ち続けられるよう、地域で活躍する大学への財政的支援について、皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。
令和6年7月4日 山形大学長 玉手 英利