


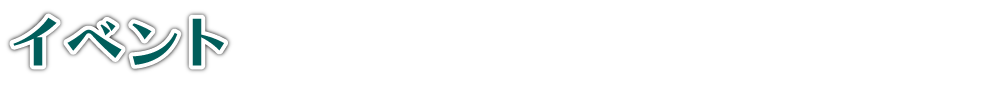



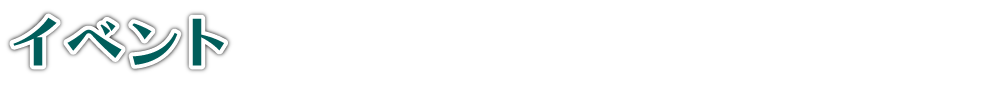
ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年07月 > 学長定例記者会見を開催しました(7/4) > 患者へのアンケートにみる 地域による「重粒子線治療」認知度の違いと 小藤昌志教授の重粒子線治療センター長就任について ~山形大学医学部東日本重粒子センター~
掲載日:2024.07.04
1.患者へのアンケートにみる地域による「重粒子線治療」認知度の違い
本件のポイント
東日本重粒子センターでは、治療の最終日に患者さんにアンケートにご協力いただき、その結果を設備の新設・改修やサービス向上に反映させてまいりました。
令和6年2月からアンケート様式を一部変更し、新たに「お住まいの地域での重粒子線治療の認知度」についての質問を設けました。2月から5月までの4か月分を集計した結果、山形県内では認知度が75%であるのに対し、県外では、そのおおよそ3分の1の27%にとどまることが明らかになりました。
旧様式:令和3年4月~令和6年1月 アンケート協力者数:1,342人
新様式:令和6年2月~令和6年5月 アンケート協力者数: 219人
詳しくは、こちら(リリースペーパー)をご覧ください。

アンケート集計結果
お住まいの地域での重粒子線治療の認知度はいかがでしょうか?
県内
| 選択肢 |
ほとんど 知られていない |
ある程度 知られている |
多くの人が 知っている |
わからない |
| 回答(%) | 13.8% | 57.2% | 17.9% | 11.0% |
県外
| 選択肢 |
ほとんど 知られていない |
ある程度 知られている |
多くの人が 知っている |
わからない |
| 回答(%) | 57.7% | 25.4% | 1.4% | 15.5% |
今後の展望
がん対策基本法においては、第二条に基本理念として、「がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること。」(がん医療の均てん化)と明確に謳われています。本調査では、重粒子線治療の認知度が施設設置県とそれ以外の県で著しく差があり、この点における均てん化には程遠いことが明らかになりました。当センターでも県外メディアに向けた広報活動は積極的に行ってきましたが、認知度を県内並みにアップするにはまだまだ質・量ともに不足していたと分析しています。
この結果を受けて、当センターでは9月30日に青森市で、12月15日に山形市で一般市民向け公開セミナーを開催するなど、今後も県内外で継続して当センターにおける重粒子線がん治療に関する情報提供に努めます。
2.小藤昌志放射線医学講座放射線腫瘍学分野教授が附属病院重粒子線治療センター長に就任
出身大学:東北大学医学部 1996年3月卒
1996年~聖路加国際病院内科
1999年~東北大学病院放射線治療科
2005年~米国 MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Radiation Oncology
2007年~東北大学病院放射線治療科
2010年~量子科学技術研究開発機構(旧放射線医学総合研究所)
2020年より放射線医学総合研究所 重粒子線治療研究部 部長
2023年より放射線医学研究所 副所長
2024年7月1日より現職