


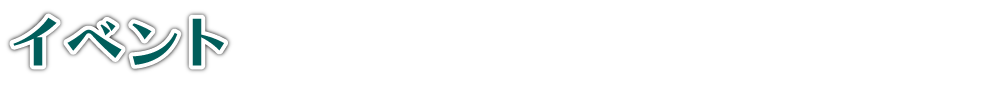



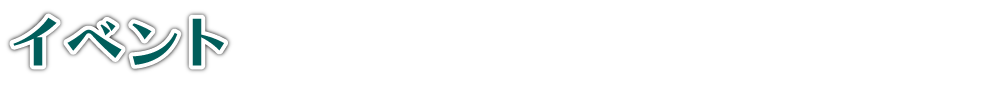
ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年01月 > 学長定例記者会見を開催しました(1/16) > 並河英紀教授が第42回(2024年度)日本化学会学術賞を受賞 ~学際的な自己組織化の研究を進め、独創的な研究分野を開拓~
掲載日:2025.01.16

並河英紀教授(理学部主担当・理学部長)が第42 回日本化学会学術賞を受賞しました。この賞は、わが国最大の化学系学会である日本化学会から授与されるものであり、先導的・開拓的な研究業績をあげた研究者に贈られるものです。今回の受賞は、並河教授が山形大学に着任した2011年以降行ってきた自己組織化に関する基礎的かつ学際的な研究成果が高く評価されたものです。山形大学では初、東北地方でも東北大学以外での受賞は初めてとなります。受賞研究題目は「非線形・非平衡系における自己組織化に関する研究」であり、3月26日から関西大学で開催される日本化学会第 105 春季年会(2025)において記念講演ならびに授賞式が行われます。
詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。
自己組織化とは、物質などが自ら集合し、規則的な構造や秩序を構築する現象を指します。例えば、水分子が自己組織化して規則的な構造を作ったものが氷であり、洗剤に含まれる界面活性剤分子が油汚れを落とすために形成するミセルも、自己組織化によって自ら作り出す構造の一つです。他にも、細胞膜は脂質分子が自己組織化したもの、熱帯魚の綺麗な縞々模様は色が異なる色素細胞が自己組織化したものなど、あらゆる分野で自己組織化による空間的あるいは時間的な秩序構造の仕組みが組み込まれています。自然科学分野だけではなく、社会科学分野にもあります。例えば、2008年ノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンは、都市がどのように構築されるかを自己組織化の観点から研究しています。このように、「自己組織化」は、化学や生物、地球、宇宙、社会・経済といった幅広い分野で注目されている学際的で普遍的な原理です。
前述のように非常に多岐にわたる分野においてみられる自己組織化ですが、構造形成の過程の違いによって「平衡系の自己組織化」と「非平衡系の自己組織化」に分けられます。並河教授は、2011年の本学着任以降、この両方の自己組織化に関する研究を進めてまいりましたが、そのうちの「非平衡系の自己組織化」に関する独創的な研究成果が高く評価されました。その内容は大きく分けて次の二つがございます。
(1) リーゼガング現象に関する研究
リーゼガング現象とは、ドイツ人科学者のRaphael Edward Liesegangが1896年に発見した自己組織化現象です(冒頭の写真)。シャーレや試験管でも簡単に実験できるにもかかわらず美しい模様が浮かび上がることから、一般の方が興味を持たれたり、高校の探究学習などでも活用される実験題材となっております。これまでに県外のアマチュア鉱物採集家の方から質問を受けリーゼガング現象と岩石模様についての議論を行ったことや、実験方法やシミュレーション方法を指導した高校生が、高校生・高専生科学技術チャレンジで朝日新聞社賞を受賞し、ISEF2024(国際的な集会)へ出場したこともございます。
この様に実験は非常にシンプルでありますが、非線形過程と呼ばれる複雑な反応機構を含んでいることから、発見から100年以上たっても美しい模様を形成する反応機構の全貌解明には至っておりません。その様な中、並河教授はリーゼガング現象に関する二つの提案モデルを統合した画期的なモデルを提案し、自然界で見られる類似の自己組織化構造の形成機構を解き明かすカギとなる新たなアプローチを提案することに成功しました。
(2) アミロイドβ(Aβ)タンパク質の自己組織化に関する研究
Aβタンパク質が脳の中で自己組織化をすることが、アルツハイマー病の発症に関わっていると考えられています。その為、アルツハイマー病の発症機構を理解するために、Aβタンパク質の自己組織化に関する研究が世界中でおこなわれています。並河教授は、脳内における特殊な環境(=非平衡状態)がAβタンパク質の自己組織化に影響を及ぼしていることを突き止めました。本成果は、アルツハイマー病に関する分子メカニズムの理解にとどまらず、生体内の自己組織化が関与する多くの疾患等に関する新たな知見を発掘する可能性も有し、さらに、自己組織化を用いた高機能材料開発などへの応用も期待される成果になりました。
冒頭の「自己組織化」で記述した通り、自己組織化は、化学分野だけではなく、生命、地球、宇宙、そして社会科学など、あらゆる分野に普遍的な時空間的な秩序を作る原理として働いています。その中での化学者としての使命は、他分野でもみられる自己組織化を化学反応を用いて再現し、その反応機構を解明することで、自然界でみられる自己組織化に共有する普遍的な原理を発掘・理解することです。引き続き、様々な自己組織化現象について化学的な視点から原理を追求する研究を進め、得られた知見を、他の自然科学・社会科学分野へ還元できるような学際的研究を先導して参りたいと思います。
今回の受賞は山形大学に在籍していた13年間の研究成果に評価を頂いたものでありますが、この13年間の半分以上となる7年間は、副学長特別補佐(2年間)、理学部副学部長(3年間)、理学部長(現在3年目)と、学部・大学運営に携わってまいりました。この様に研究時間が制限された中でも国内外でも高く評価を頂ける研究活動を進めることができたのは、一緒に研究を進めてきた山形大学理学部学生・大学院生の能力の高さを示すものに他なりません。理学部では、学術的な知の創出を使命として、その観点から専門性を重視した教育を展開しています。一方で、現代社会が求めるコミュニケーション能力や課題解決力など、多様なスキルを養う新しいカリキュラムにも積極的に注力しています。引き続き、専門知識と社会的スキルを兼ね備えた人材を輩出し、地域社会の発展に貢献できるよう、研究者として、また、理学部長として、教育・研究環境の整備を進めて参りたいと思います。