


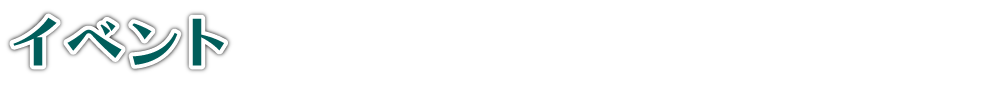



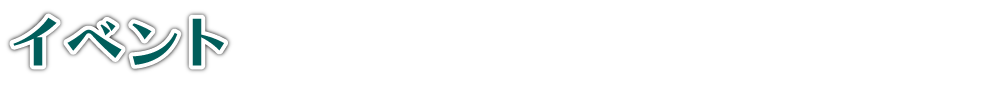
ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年04月 > 学長定例記者会見を開催しました(4/10) > 理工学研究科の安達茜さんが第15回日本学術振興会育志賞を受賞
掲載日:2025.04.10

安達茜さん(理工学研究科地球共生圏科学専攻・博士後期課程3年)が第15回(令和6(2024)年度)日本学術振興会育志賞を受賞しました。この賞は、上皇陛下の天皇御即位20年にあたり、勉学や研究に励んでいる若手研究者を支援・奨励するために創設され、将来我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生に送られる賞です。今年度は全国の大学・学会等からの177名の推薦のうち19名が受賞となりました。今回の賞は、安達さんが博士課程までに進めてきた、分子科学的視点におけるアミロイドβの初期凝集に関する研究が高く評価されたものです。受賞研究題目は「脳間質液流動を模倣した開放系におけるアミロイドβ分子の凝集機構解明」で、2025年3月6日に日本学士院にて授賞式が執り行われました。
詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。
アルツハイマー病はアミロイドβ(Aβ)タンパク質が脳内で凝集し脳細胞表面に吸着する特徴を有しています。脳内は間質液と呼ばれる脳内を満たす溶液が常に流動する環境(開放系)を維持しており、この環境においてAβの凝集や吸着が進行します。特に初期の凝集や吸着を阻止することが急務とされています。本研究では、脳内を模倣した環境にて1分子レベルでAβを追跡できる実験系の構築に成功し、開放系がAβの凝集や吸着のみならず、その性質をも変化させる可能性を見出しました。アルツハイマー病の発症機構の初期段階から開放系を考慮する必要性を提唱し、機構解明への橋掛かりとなる成果になりました。
アルツハイマー病は、発見から100年以上経っても完治することのできない病気です。発症機構から創薬まで、未解明な部分は多々あります。引き続き、化学の視点からアルツハイマー病の発症機構解明に尽力し、薬学や医学、工学等の分野を横断した知識を吸収し新しい発想に繋げながら、学際的研究を進めて参ります。
今回の受賞は、研究を基礎から教えてくださった並河英紀教授をはじめ、家族や支えてくださった皆様のおかげです。今回の受賞を糧にし、さらなる新しい発見をするべくより一層研究に精進する所存です。また、現在は博士後期課程と並行して、本学の地域共創STEAM教育推進センターにてプロジェクト教員も兼任しております。今後は、次世代の子ども達に科学や研究の面白さを伝えるために、教育にも力を入れて参ります。