


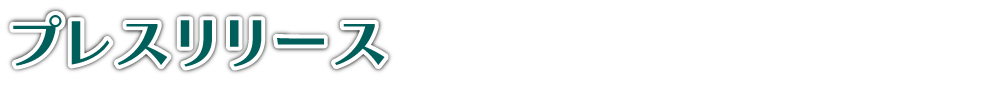



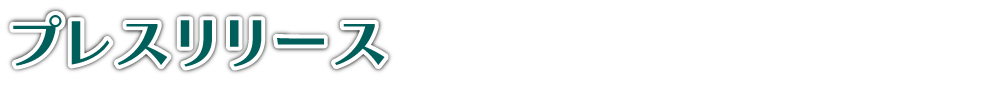
ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年03月 > ナスカ地上絵の論文が2024年 PNAS Cozzarelli Prizeを受賞!
掲載日:2025.03.12

山形大学ナスカ研究所とIBM研究所の共同研究研究で発表した論文 "AI-accelerated Nazca survey nearly doubles the number of known figurative geoglyphs and sheds light on their purpose " (AIによってナスカ調査が加速したことで、既知の具象的な地上絵の数がほぼ倍増し、地上絵の目的が明らかになった。) が、2024年 PNAS「Cozzarelli Prize」(コッツァレリ賞)を受賞しました。
本賞は、2024年にPNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences、米国科学アカデミー紀要)に掲載された3,200本以上の研究論文の中から、優れた6本を選び表彰するものです。これら6本の論文は、米国科学アカデミーの6つの部門(物理・数学科学、生物科学、工学・応用科学、生物医学科学、行動科学・社会科学、応用生物・農業・環境科学)に対応しています。2025年4月27日、米国科学アカデミー年次総会の授賞式で表彰される予定です。
なお、行動・社会科学部門において、日本の大学に所属する研究者としては初めての受賞となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
過去1世紀にわたり、ペルー南海岸のナスカ台地で、動物や人間などを描いた具象的な地上絵が430点発見されました。本研究では、この地域の航空写真をAIで分析し、6か月にわたる現地調査を経て、新たに303点の「具象的な地上絵」を確認しました。これらの地上絵のモチーフを分析したところ、小型の面タイプの「具象的な地上絵」には人間や家畜、あるいは首をはねられた頭部が多く描かれている一方、大型の線タイプの「具象的な地上絵」は主に野生動物を表していることが明らかになりました。
さらに、小型の面タイプの「具象的な地上絵」は、繰り返し人が歩いたことで形成された曲がりくねった小道に沿って分布しているため、個人や小集団によって利用されていた可能性が高いと考えられます。一方、大型の線タイプの「具象的な地上絵」は、ナスカ台地を横断するために体系的に整備された巡礼路の起点と終点に配置されていることから、公共的な建造物として機能していたと推測されます。
論文についてはこちらからご確認いただけます。(https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2407652121)
この論文の筆頭・責任著者である坂井正人は、大学院生時代の1994年にナスカの地上絵の研究を始めました。当初は踏査による予備調査を実施しましたが、ナスカ台地が約400平方キロメートルと広大であったため、調査は難航しました。その後、山形大学に赴任し、2004年からは同大学において環境地理学・認知心理学・情報科学の専門家と学際的な共同研究を立ち上げ、人工衛星画像を活用した地上絵の分布調査を進めました。さらに2012年には、現地調査を効率的に行えるように、山形大学はナスカ市に「山形大学ナスカ研究所」を設立し、高解像度航空写真やドローンなどのリモートセンシング技術を活用した結果、合計314点の新たな「具象的な地上絵」を発見しました。
しかし、ナスカ台地は非常に広大なため、リモートセンシング技術を活用しても現地調査には膨大な時間と労力がかかります。そこで研究の効率化を図るため、IBMの協力を得て人工知能(AI)を用いた現地調査を行ったところ、わずか6か月間で303点もの新たな地上絵を発見することに成功しました。
さらに、これらの「具象的な地上絵」が何の目的で制作されたのかを解明するため、地上絵の近くにある「直線の地上絵」や小道を調査した結果、大型の線タイプの「具象的な地上絵」は神殿や聖地へと通じる巡礼路の出発点と終着点に設置され、共同体の儀礼用広場として機能していたことが分かりました。一方、小型の面タイプの「具象的な地上絵」は、小道を通る個人や小集団に社会的に重要な情報を伝える「掲示板」としての役割を担っていた可能性が高いことを明らかにしました。
今回の受賞は、IBMとの共同研究がなければ実現し得なかったと考えています。また、20年以上にわたり山形大学でのナスカの地上絵研究を支えてくださった歴代の学長・執行部・事務局、日本とペルーの共同研究者、学生・若手研究者の皆さまに深く感謝申し上げます。最後に、母と妻に対して、特別な感謝を捧げたいと思います。
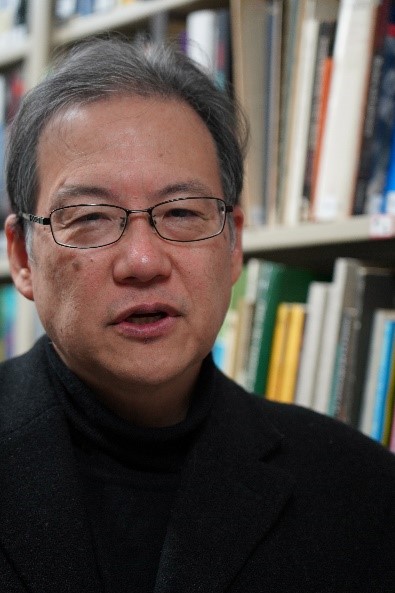
今回の研究によって、地上絵の制作目的について大まかな理解が得られました。
しかし、いまだ数百点もの地上絵が未発見のまま残されているため、最新のAI技術を活用した現地調査によってそれらの分布を網羅的に把握するとともに、そこに込められた意味を解読することが第一の目的です。
また、最新のAI技術は、地上絵の分布調査だけでなく解読作業にも活用する予定です。今回の受賞を契機に、ナスカの地上絵の解読作業をさらに進めたいと考えています。人文社会学系の研究領域において、最新の人工知能を活用するための指針となるような研究を展開できればとも思っています。
さらに、21世紀に入ってから地上絵の破壊が加速している現状を踏まえ、これらを保護する活動を推進することも、もう一つの重要な目的となります。