


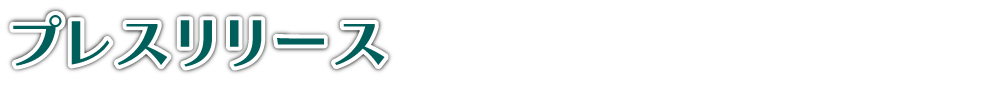



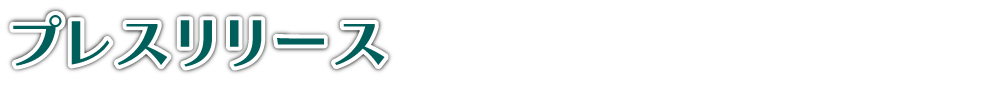
ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年03月 > 「なぜ山形でナスカなのか」 学長所感
掲載日:2025.03.12
Why Nazca in Yamagata? なぜ山形大学がナスカ地上絵の研究をしているのか、という質問をよく受けます。
山形という日本の地方都市にある大学が、地球の反対側に位置するナスカの地上絵研究で大きな業績を上げたことは、一見すると意外に思われるかもしれません。しかし、これは偶然の産物ではなく、世界的な研究を生み出す3つの要因が山形大学に揃っていたからです。
第1の要因は、山形大学にナスカ地上絵の研究を志した研究者がいたこと
世界中のどこにいても真理を探究する科学者の姿勢に変わりはありません。これを「学問の自由」と呼びます。ナスカの地上絵に学問的興味をもち、粘り強く研究を続ける研究者が、たまたま山形大学にいたことが、この研究の出発点となりました。
第2の要因は、山形大学とペルーでこの研究を支えた人々がいたこと
日本とペルーの共同研究者や学生はもとより、人文社会科学部をはじめとする山形大学とペルーの現地で研究を支える人々がいました。このような人々がいなければ、20年余にわたる長期の基礎研究を続けることはできませんでした。
第3の要因は、山形大学が長期的な視野に立って研究環境の整備をおこなったこと
山形大学は、2004年からナスカ地上絵の共同研究の組織的支援を開始しました。2012年には大学の自己財源でペルーの現地に山形大学ナスカ研究所を建設し、20年以上の長きにわたり、ナスカ地上絵の研究を全学的な重点研究プロジェクトとして支援してきました。主な研究資金は、山形大学及び共同研究を行う各大学の研究者が受けた科学研究費で支えられています。しかし、科学研究費の採択率は3割未満(基盤研究の場合)で、常に採択されるとは限りません。採択されない時は大学運営資金で研究を支えてきました。
日本の国立大学が外部資金への依存度を高め、短期間で成果が出る研究がより重視されるなかで、地道で息の長い基礎研究は衰退しつつあります。特に人文系の基礎研究は、すぐに目に見える形で社会に貢献するとは限りません。しかし、時間をかけて培われた知見は、やがて社会の知的財産となり、新たな発見や国際的な対話の礎となります。山形大学のナスカ地上絵の研究が国際的に高く評価されたことは、地方大学においても世界に通じる研究が可能であり、そのためには高い志をもった研究者に対する長期的な支援が不可欠であることを示しています。
しかし、国立大学の主な財源である運営費交付金は山形大学の場合、毎年約9000万円減らされています。そのため、ナスカ地上絵のように外部資金の調達が困難な基礎的研究を持続することはますます困難になっています。ナスカ研究所の維持経費として200~300万円程度の資金が必要ですが、その調達にも苦労しています。山形大学では地上絵の研究を支援するナスカ基金を設けています。どうか多くの皆様のご支援を賜りますようにお願い致します。
地方国立大学の衰退は日本の研究力の凋落を加速化させます。国際卓越研究大学に毎年百億円単位での資金が重点投下される日本の社会において、わずかな額の研究費を確保するために苦闘する研究者や大学・学術機関があることも皆様に知っていただきたいと思います。
山形大学学長 玉手 英利
(参考)ナスカ研究所のHP https://www.yamagata-u.ac.jp/nasca/index.html
ナスカ基金 https://www.yamagata-u.ac.jp/nasca/fund/