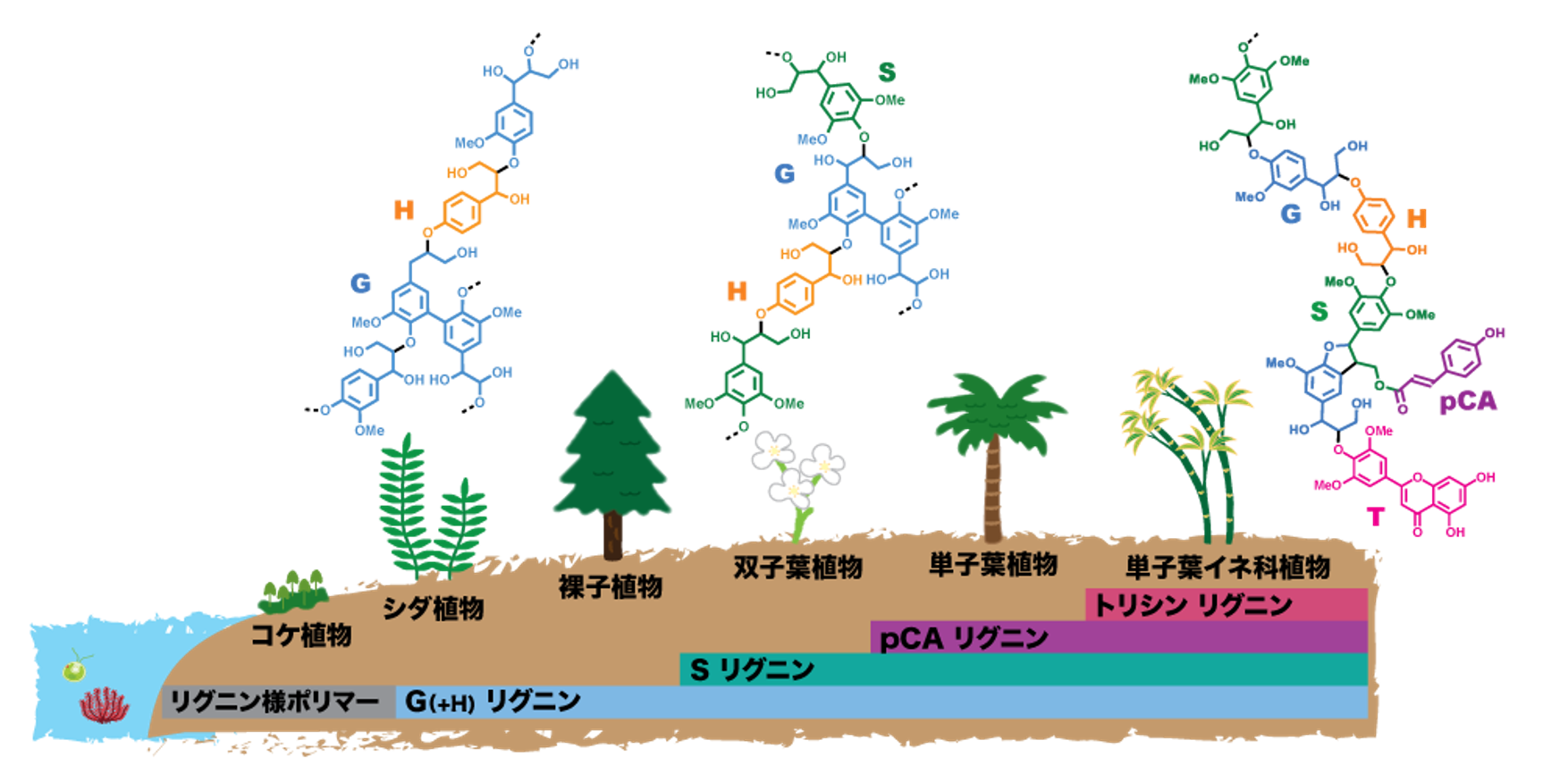
農学
ゲノム情報から探るリグニン代謝の進化
2025.07.01


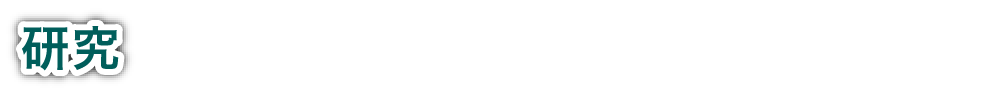
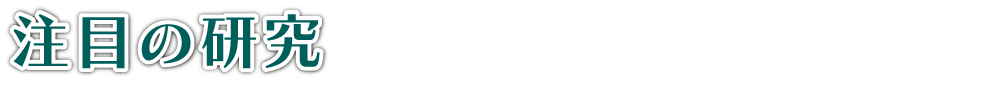
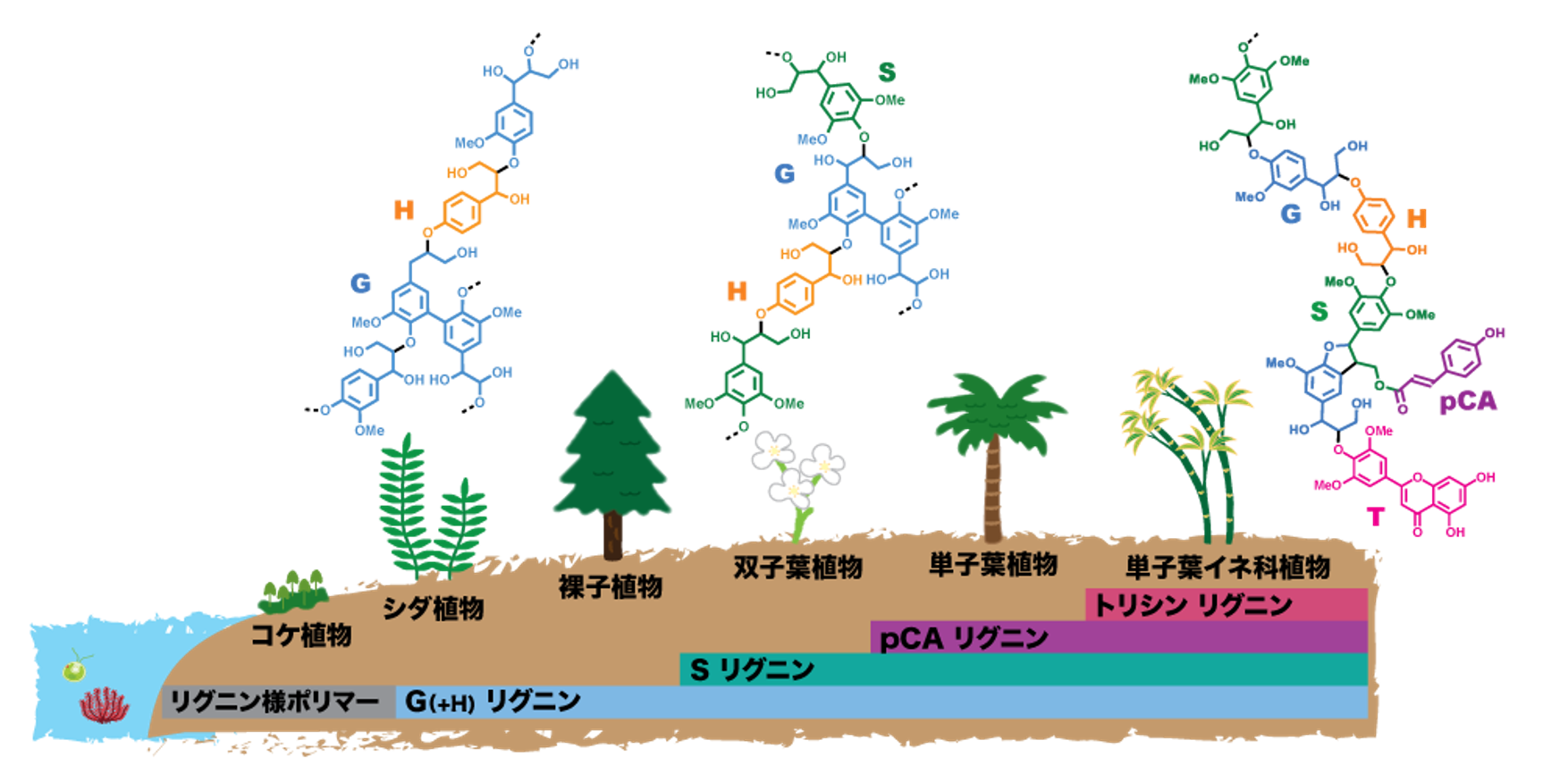
農学
ゲノム情報から探るリグニン代謝の進化
2025.07.01
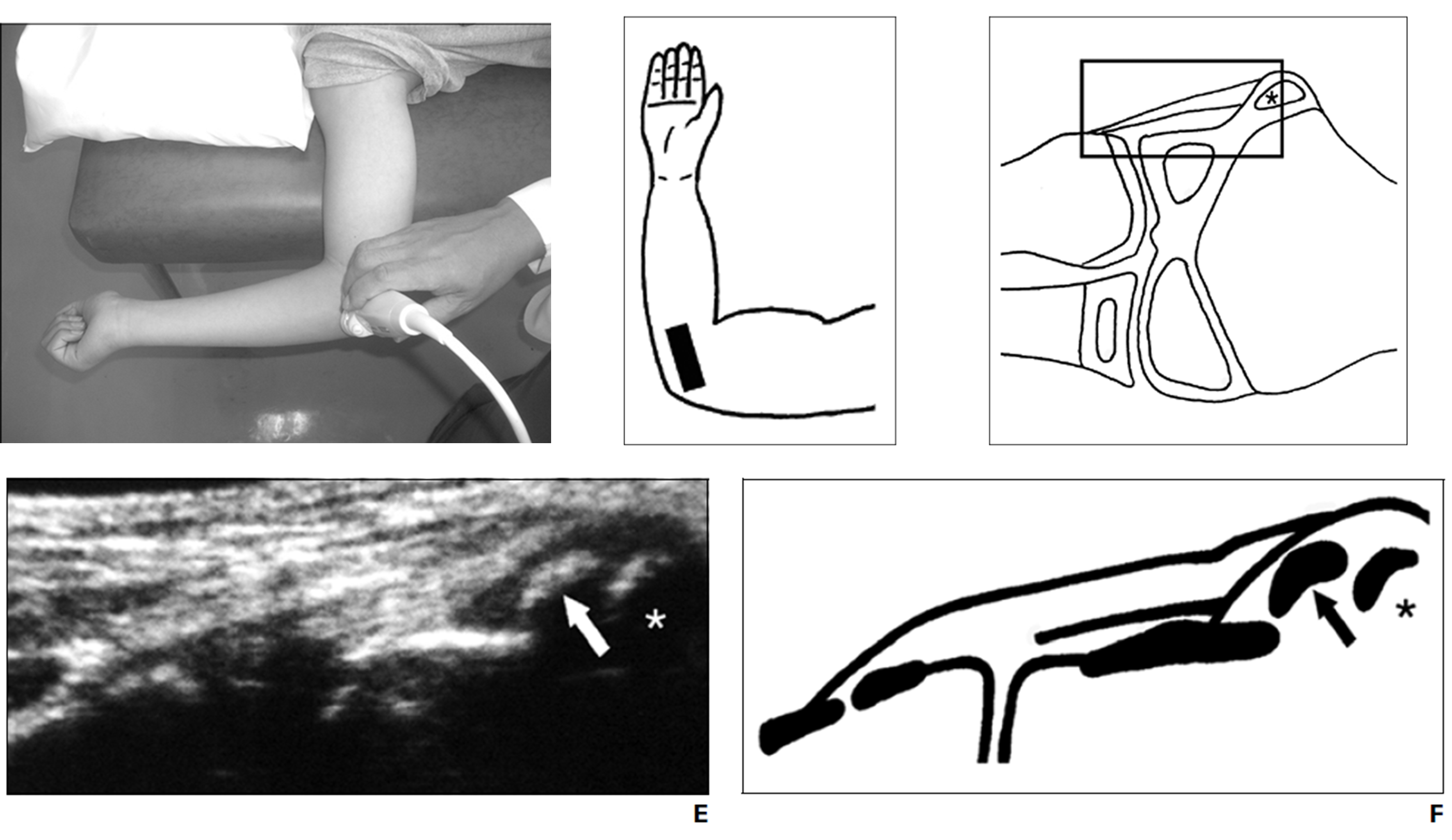
医歯薬学
5-ALAによるサルコペニアの予防・改善
2025.06.23

教育学
認知特性を活かした長所活用型指導
2025.06.11

その他
Well-beingに貢献する観光地域づくりの検討
2025.06.02

社会科学
地場産業の持続的発展をめざして
2025.05.21
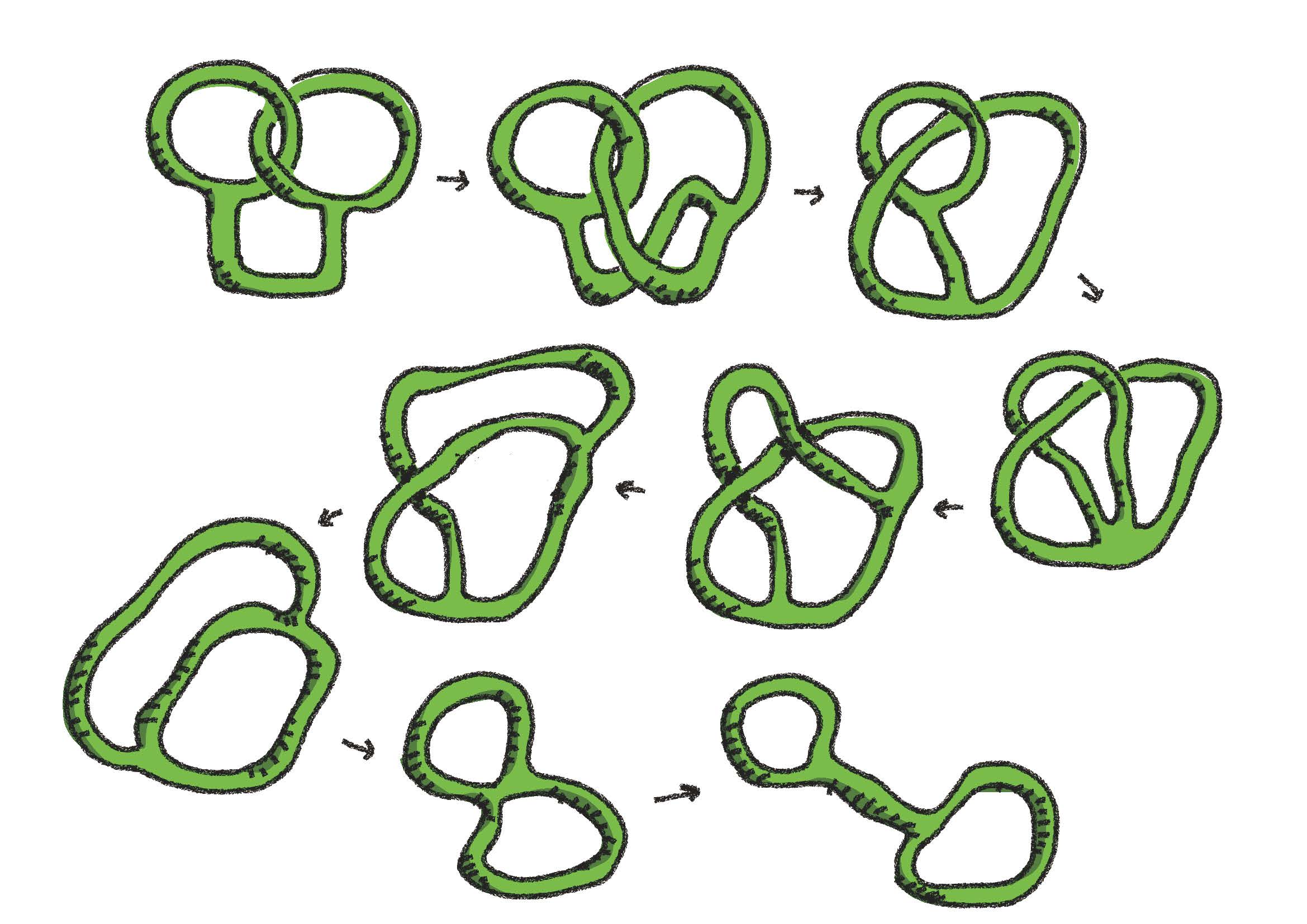
数物系科学
トポロジカル ソリトン:宇宙の化石
2025.05.12

農学
果実の発達と品質を科学する
2025.05.01
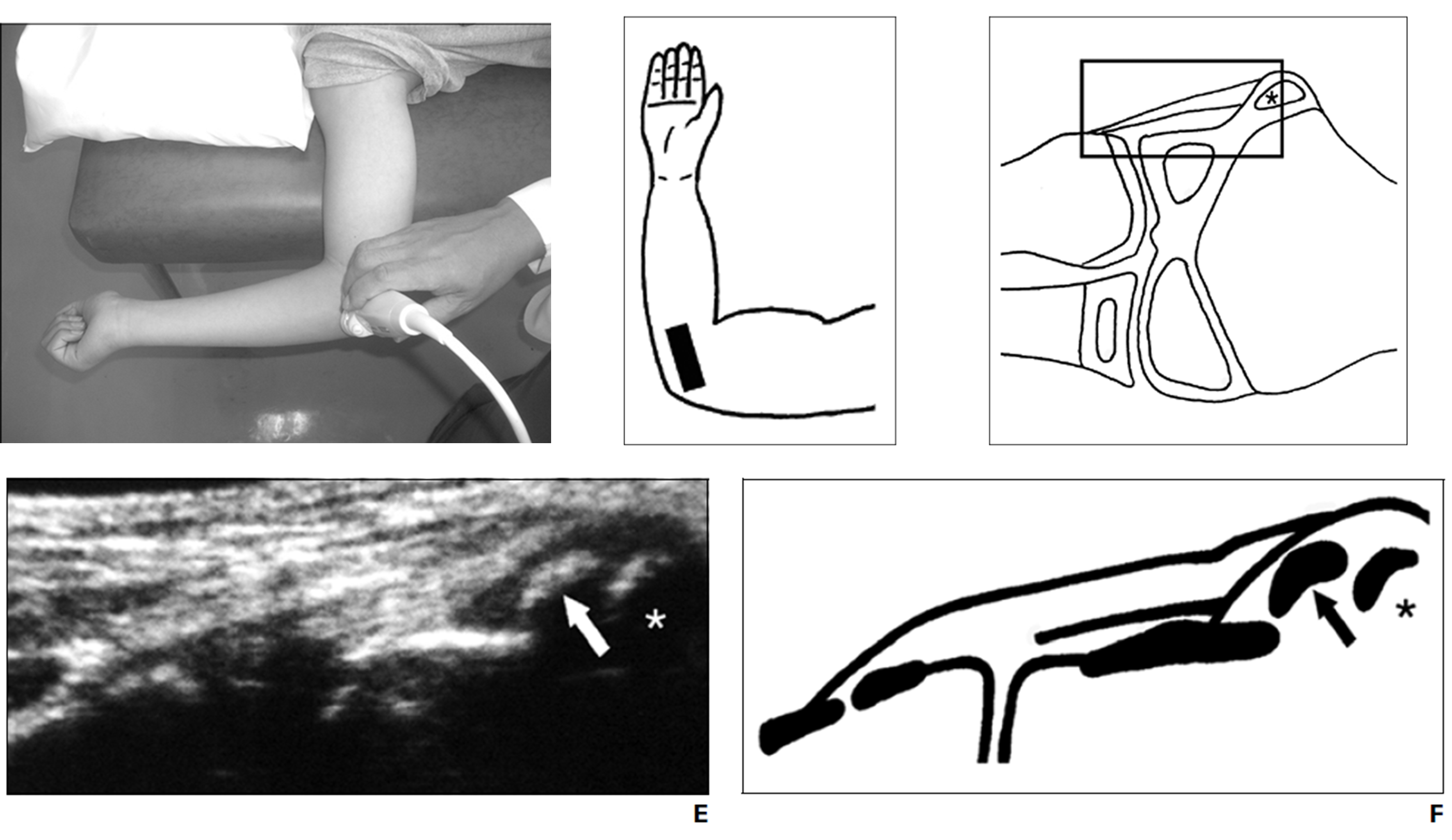
医歯薬学
野球肘の病態解明と運動器再生治療の基礎研究
2025.04.21
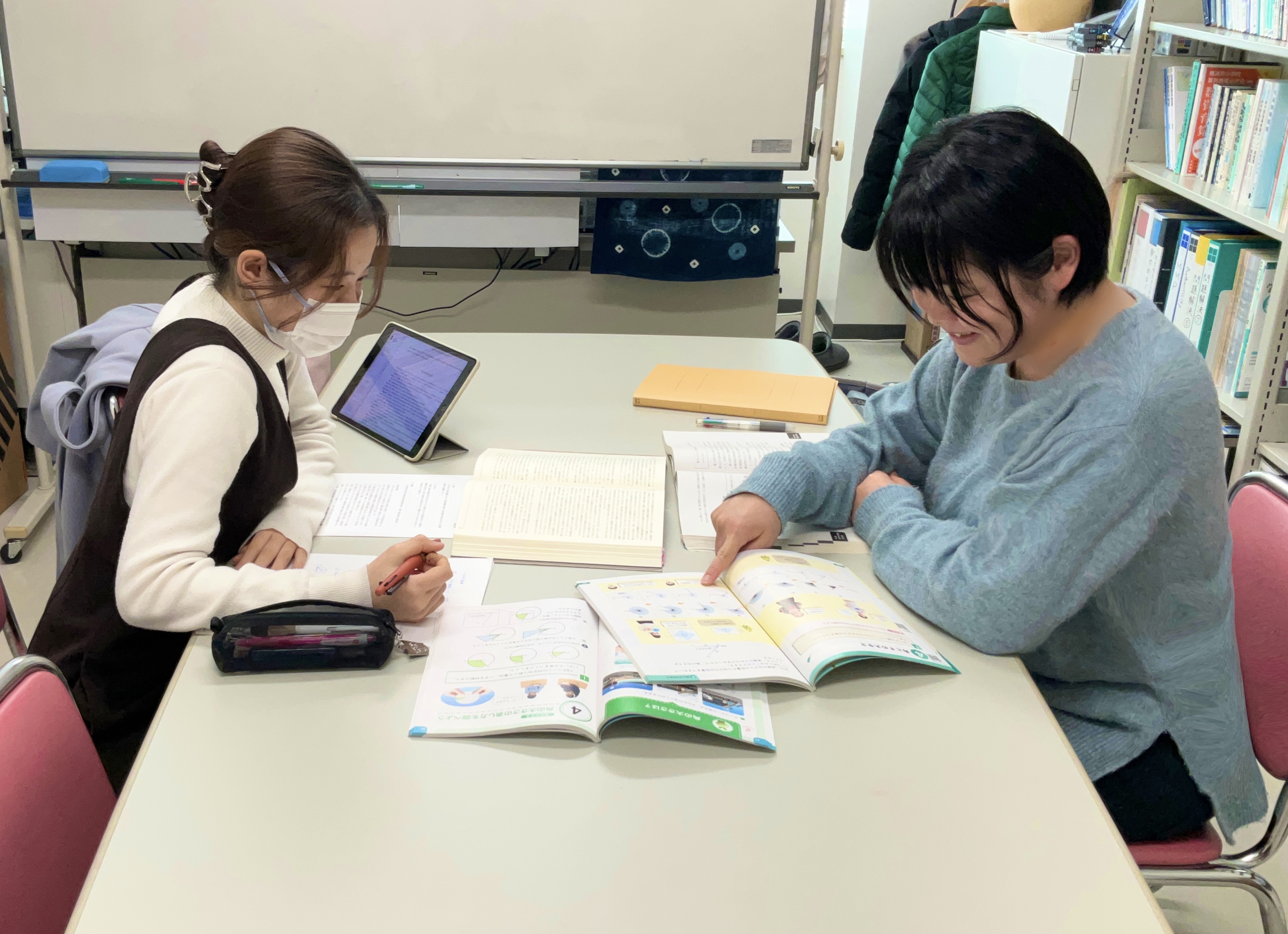
教育学
算数・数学の楽しさを伝えるには
2025.04.11
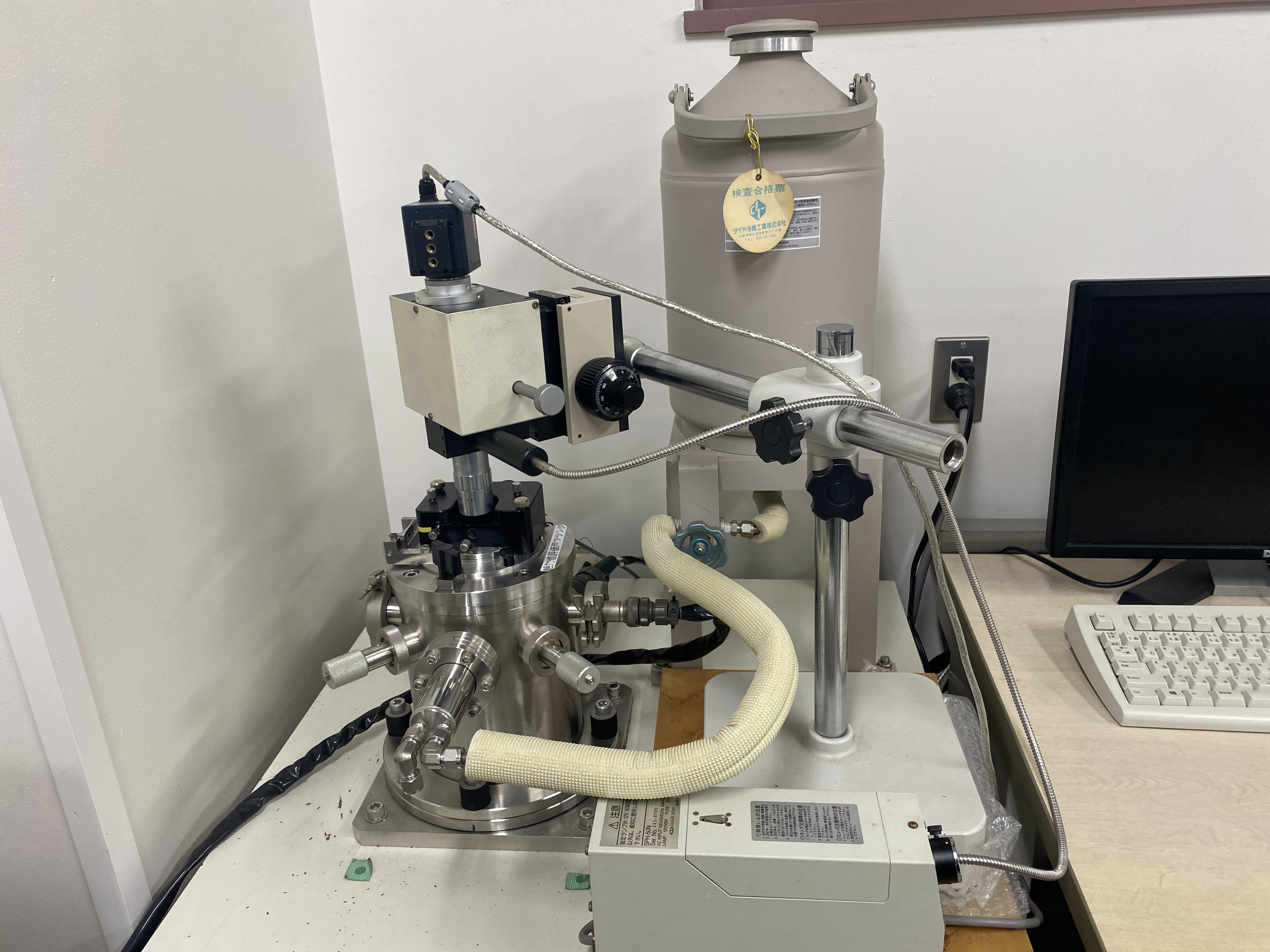
工学
高分子の分解過程を視覚化し理解する
2025.04.01
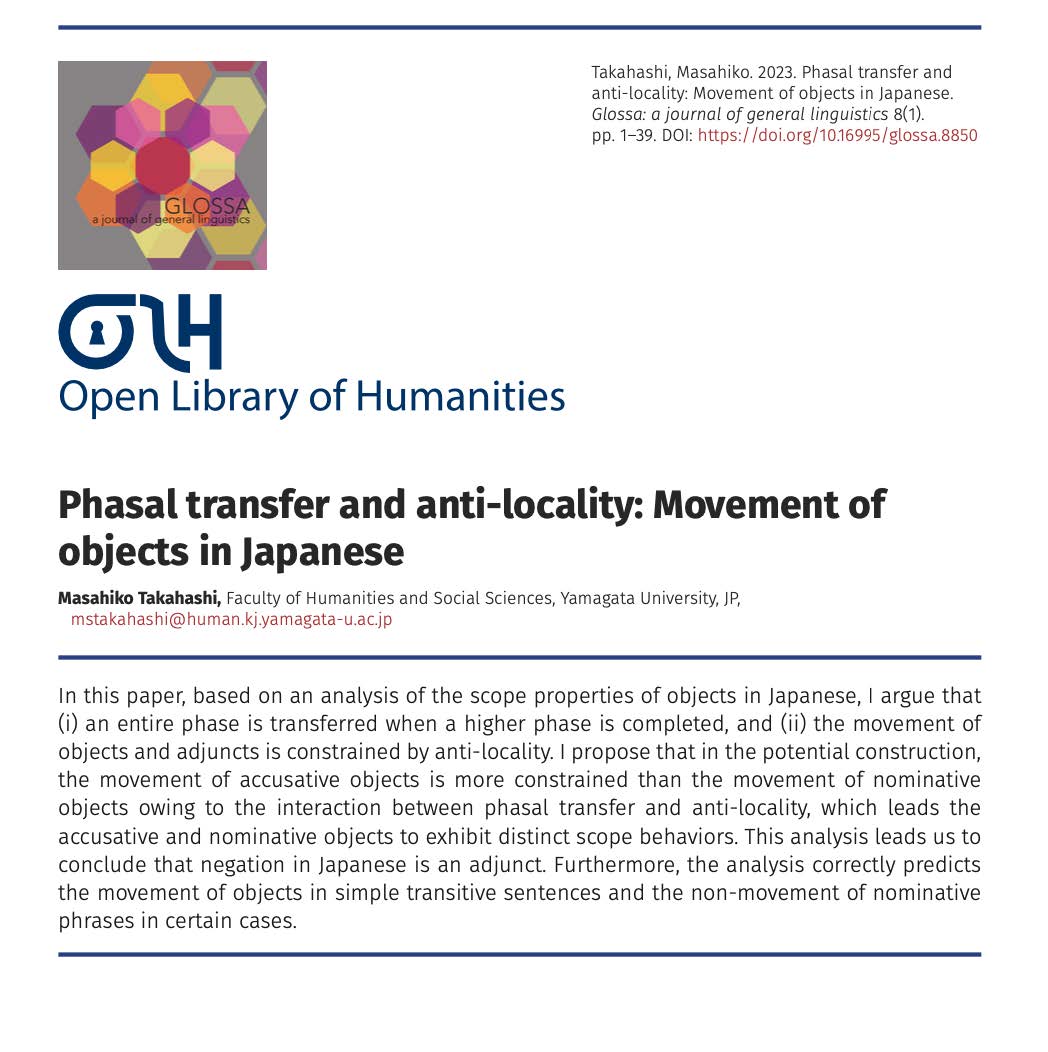
人文学
無意識のことばの知識
2025.03.21
生物学
特殊な環境に生息する昆虫の多様性
2025.03.11
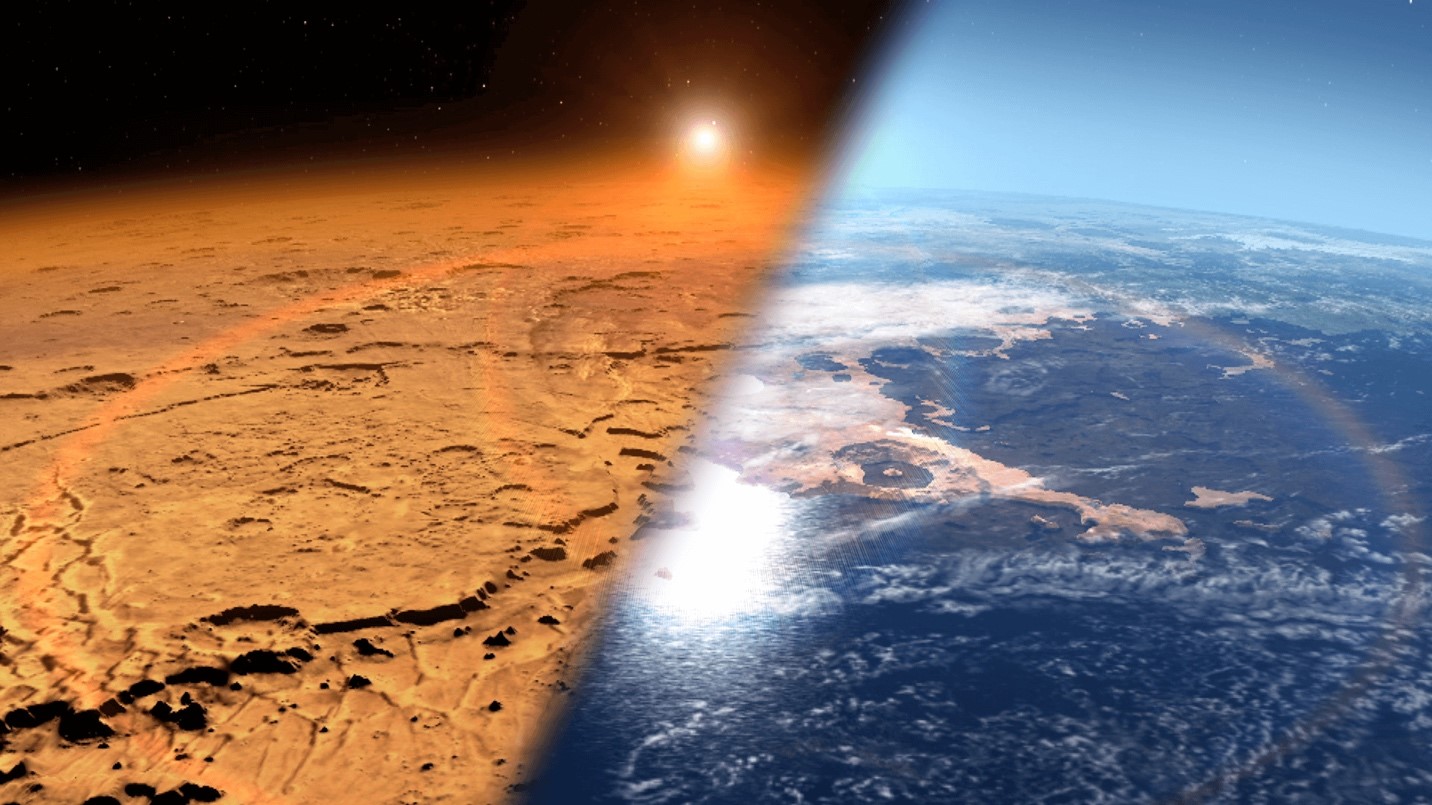
その他
火星の海の行方を探る
2025.03.03

環境学
極寒の南極と灼熱のエチオピアで地球を探る
2025.02.03
医歯薬学
妊娠中のEPA/DHA摂取量と低出生体重児との関係
2025.01.21