

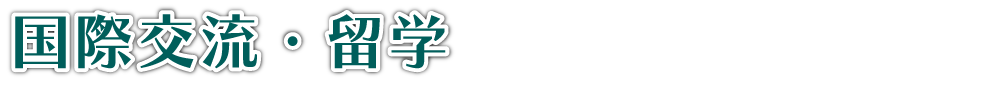


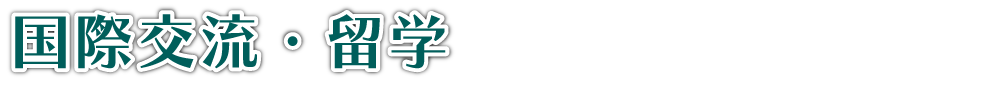
ホーム > 国際交流・留学 > 学生大使派遣プログラムについて > R1ガジャマダ大学 > 小澤諒三
派遣先大学・派遣先期間 ガジャマダ大学 8月25日~9月15日(9月17日)
日本語教室での活動内容
日本語教室は月曜日から金曜日までの週5日、午前は10時~11時30分まで、午後は13時30分~15時までの一日二回行った。来る人はガジャマダ大学生にとどまらず、ジョグジャカルタの付近の大学の大学生や高校生、社会人と年齢や性別に関係なく日本語教室に参加していた。日本語教室の門をたたく生徒の皆に共通して言えることは日本に強い関心があり、目的意識をもっているということだ。しかし日本語の技能は人によってそれぞれだったので相応のレベルに応えるために日本語教室は初級、中級、上級の三段階に分け、月曜日から木曜日は日本語を教え、金曜日は日本の文化の紹介を行うことを目的とした形式の授業をクラスで行った。山大生の数が増えるにしたがって山大生間での情報の共有が難しくなり始めたため全ての階級をまんべんなくローテーションできるようなシフトを組み、それに従って活動の方針を決めることで授業の進捗状況や受講生の特徴を共有し講義の秩序を保つことに努めた。使う教材はインターネットでコミックやテキストを引用し、時には生徒の期待に応えるべく関西弁(京都弁)を教えることもあった。階級が高くなるにつれて日本語を学習することに対する具体的な目的意識を持つ生徒が多くなる傾向が強いため中級や上級のクラスの場合は個別性を意識し、本人のニーズに出来るだけ沿った授業(前述した関西弁の例など)を行うと満足気に喜んでくれた。自分の場合、紙の教材は定型的である故、それらの要望にうまくマッチさせることが困難になるため使用は控え、「普段の生活においてできないこと」「教科書には載っていないこと」に焦点を当て、対話を意識した講義を行った。また階級によっては英語よりも日本語の方が得意だという生徒もおり、日本語のレベルは事前に伺っていた通りかなり高かったため、英語で話すよりもまず日本語で話し、伝わらなかった部分を英語で解説する。または生徒がわからなかった単語のみを英語で伝える形式で授業を行った。
初級
・日本語の文型 ・ひらがな、カタカナ
・ボキャブラリー ・簡単な会話、文章 etc
中級
・文法 ・漢字
・助数詞 ・オノマトペ
・より複雑な会話、文章 ・簡単な作文 etc
上級
・オノマトペ ・自由作文
・ことわざ、慣用句 ・スラング(若者言葉など) etc
日本語教室以外での活動内容
休日は基本的に日本語クラスの皆と学生大使のメンバーでタクシー、レンタカー、バイクといった交通手段でジョグジャカルタの観光地に足を運んだ。
訪れた観光地
・タマンサリ ・ボロブドゥール遺跡
・グンビラロカ動物園 ・クラトン
・プランバナン遺跡 ・ビーチ(名称不明)
・夜景のきれいな山(名称不明) ・マリオボロ通り
平日の朝は学生大使のメンバーで学校の食堂でご飯を済ませ、昼休みは日本語クラスの生徒と食堂に行き交流を深めた。授業後日本語クラスの生徒と食事やショッピングを楽しみ、時には学生大使のメンバーの誕生日を共に祝った。またインドネシア人の学生に髪の毛の色を変えてみないかと言われ興味本位で髪を切るついでに染めることになり最終的にインドネシアに滞在しているうちに三回髪色が変わった。(茶色?⇒黄色⇒ピンク⇒青)それとインドネシアの伝統的な調味料サンバルには気を付けた方がいい。かけ過ぎると涙が無意識に出てくる。しかしながら慣れてくるとおいしいから困ったものである。最後の週は盲腸?になり、倒れて入院した。何とか先生と現地の学生に助けていただいたものの先生方を含め皆に迷惑をかけた。山形を紹介する報告会に参加することができなくなってしまった。これを書いている今も少し痛い。
参加目標の達成度と努力した内容
自分の今回の滞在の目標は「新たな価値観を身に着ける」ことだ。これはまさに大成功と称しても差し支えないだろう。特に生活の中に強く根付くイスラム文化は非常に興味深いものが感じられた。自分は物心がついてから海外に行ったのはこれが初めてであったため初めて他の文化と触れ合うこととなった。嗚呼、これが俗にいうカルチャーショックなのだと非常に感銘を受けた。純日本人家系に生まれ、一般的な(そうだと信じたい)日本人として育てられた自分にとって何気ない日常に宗教的な価値観によって考え、行動が制限、拘束されるということに対して多少なりとも苦痛に感じているのではないかという先入観を持ち合わせていたが現地の学生曰くそんなことはないらしく日本人の方が堅苦しそうで大変そうだとそのまま言った言葉を返されてしまった。まさに彼の言う通りでやはり狭い価値観の中で生きているとこれほどまでに当たり前が当たり前でないことに気づくことができないのかとまさにショックを受けた。我々日本人も宗教的な考えによって内容よりも形式を必要以上に重要視したがる。敬語はその典型でありルーツは神道にある。しかし我々日本人はもはやその事実に気づいてすらいないしそもそも知らないケースが多い。きっとムスリムにとっても同じようなことなのだろう。ただやはり先ほどまで一緒に仲良く話していた彼らがお祈りをするためにすぐそばのモスクで急に改まったような感じでお祈りを始めるというのはどことなく面白く不思議な光景に思えた。他の文化圏に自分を放り込むことで現地の文化だけでなく自国の文化までも今一度見つめなおすことができた。
主観的な面白い文化(現地に行って初めて知ったこと)
・音を立ててものを食べてはいけない(麺類もすすって食べてはいけない。)
・皿を持ち上げて直接口をつけてスープを飲んではいけない。
・日本だとものすごく派手に思える正装(バティック)
・髪の毛を白くしたり、黒くしたりしてはいけない。
・民族がたくさんあり、言語も島や地域によってそれぞれ
・MADE IN JAPANの信用性(走っている車やバイクは9割以上日本製)
・トイレでお尻は左手で拭く
・左手でものを渡したり、受け取ったりしてはいけない。
・病気の人のお見舞いには現金を渡す。
プログラムに参加した感想
自分は彼らの屈託のない素直さと真面目さに驚かされた。海外の情報を積極的に必死に自分たちに取り入れようとしている姿は本当に心から尊敬した。どことなく日本の明治時代のような海外に大きく目を向けた国民全体の動きや意識を感じた。きっと日本にいたらこんなにも海外への意識が強く愚直に自分の意志に基づいて物事を推し進めることができる人々がいるのだと知る余地はなかっただろう。発展途上国と言われる国の真骨頂を見せつけられ、我々はこのままではそう遠くもない間に追い抜かれてしまうだろうと確信した。インドネシアの成長には本当に著しいものが感ぜられたが一日本人としてまだまだ負けたくない。このままではいけないと危機感を感じた。皮肉なことに僕が初めて海外に行って得た一番の関心ごとは我々の国、日本であった。そして我々日本人における全体的な世界を見る目はもうとっくの昔に喪失してしまっていたのだと落胆した。でも自分はやはり負けたくない。彼らのあこがれる日本であり続けられるために自分に出来ることは必ずあると考えた。日本の看板になれるよう努めたいという使命感が生まれた。
今回の経験による今後の展望
今回の滞在で言語に対する考え方に新たな考え方が生まれた。これまで言語は母国語と英語さえできれば問題ないと考えてきた。必要か否かという実用的な部分ででしか言語と向き合うことができなかった。ただ何か国語も話せる人たちが多い中である人から面白い話を聞いた。というのも話す言語によって性格が変わるらしいのだ。インドネシア語ならまじめな性格にジャワ語なら陽気な性格に、英語なら元気な感じに、日本語ならかしこまった感じにそれぞれ変わるらしく、改めて自分のことを思い返してみると確かに英語を話すときの自分は日本語を話す時と違う自分になったようにも思う。言語には人の性格をも変えてしまう面白い特性があるのだと気づかされた。また別の言語を勉強することで別の自分が見つけられるかもしれないと考えるとわくわくする。言語を勉強する意味を自分の中で確立することができた。それに初級の人にうまく英語で説明できなかったことが心残りであるのでより言語力を高めていくことにこれまで以上に精進し、再びインドネシアの地を訪ねるときには後悔の無いようにしたい。そしてさらに日本の国に興味を持ってもらいたい。

▲ボロブドゥール寺院にて

▲日本語クラス

▲入院中のお見舞い