

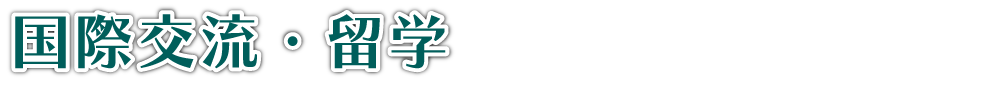


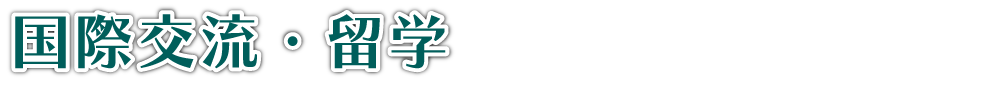
ホーム > 国際交流・留学 > 学生大使派遣プログラムについて > R1ラトビア大学 > 林咲良
派遣先大学:ラトビア大学 派遣期間:2020年02月21日~03月06日
〈日本語教室での活動内容〉
時間割は以下の通りである。
月 18:00~19:30
水 16:00~17:30 18:00~19:30
木 16:00~17:30
金 18:00~19:30
*火・土・日は休み
出国する前に前回ラトビアに行った人たちの報告書を読んで行ったが、行く時期によって、クラスの人数、時間、状況などが異なっていることが分かった。次の時期に学生大使に行く人たちは、文章に書いてあることが必ずしも起こるとは限らないので柔軟に対応する必要がある。
今回の日本語教室は発展クラスと初級クラスに分けて授業を行った。
発展クラスは全員社会人で、4・5人の受講生がいた。授業は全て日本語で行い、主に会話練習をした。初めは、それぞれがどのくらいの日本語力なのかを確認するために、いくつかの話題を用意してフリートークを行った。テーマの例としては、大学時代に勉強していたこと、将来の夢、好きな食べ物、頑張っていることなどが挙げられる。発展クラスの人は、基本的に文法を理解していて、日常生活を日本で送ることができるくらいのレベルの人が多かった。
初級クラスは、ラトビア大学の2人の学生が受講した。内容はひらがな・カタカナの書き取り練習、教室に日本語のテキストがあったので、そのテキストを元に音読して意味を確認した。また、私がテキストの分を読んで受講者が書き取る形式の小テストなどを行った。これも受講者のレベルに合わせてすすめていくのがよい。
〈日本語教室以外での交流活動〉
仲良くなった人にリガの旧市街を案内してもらった。歩いている中でおすすめのお店や観光名所、教会などを見て回った。ただ連れて行ってくれただけでなく、この場所はなぜできたのかといった歴史まで教えてくれたのでとても興味深かった。ラトビアは日本と違って島国ではないため、複雑な歴史を持っている。その過去が看板や飲食店などにおけるメニューの表記、現地の人が話せる(理解できる)言語、料理にまで反映されていると感じた。これからラトビアに行く人は、第一次世界大戦あたりからでもラトビアの歴史を少し勉強していくとよりリガの街を楽しむことができるだろう。
ラトビアは日本に比べてかなり物価が安いので、見たことがない料理やスイーツなどに挑戦しやすい。私は胃が弱いので、いくつかの料理で胃もたれを起こした。よって胃薬を持って行くことをおすすめする。LIDOに行くと、ラトビア人がよく食べている料理を食べられるので行ってみるといいと思う。
電車での移動中に英語で話すことが苦手だと話したら練習に付き合ってくれた。私はとても人見知りなので、仲良くなるのに時間がかかったが勇気を出してお願いしてみたら快く引き受けてくれたのでお願いして良かったと思っている。
〈参加目標の達成度と努力した内容〉
出国する前に立てた目標は
① 異国の文化にたくさんふれる
→日本とヨーロッパでは文化が大きく違うのでそれを体感すること
② 海外生活を通じて視野を広げる
→町並みや食事、ライフスタイルまで何もかも日本と異なる海外環境の全く違う場所で生活を送ることは私にとってストレスがかかることである。そのストレスに上手く対処して、現地文化を肌で感じることで、新しい価値観を得ることが目的を軸にして参加した。
① に関して
リガの旧市街を散歩することで、日本の建築物とは異なった建物を観察することができた。初めは日本の洋食にあたるものならヨーロッパでも見られると思っていた。しかし、実際に生活してみると、日本の洋食とは全く違った味付けであることが分かった。歴史が積み重ねた食文化を楽しむことができた。日本語クラスで日本とラトビアの文化について話しあうことで、互いの文化の理解ができた。日本がもつ文化がとても素敵なものだと気づいたのも、海外に出て客観的にみることができたからである。
② に関して
日本とラトビアでは生活環境が異なる。お風呂・トイレが共用、日本の味付けとは違う料理、連日新しい人とお話しするなど、初めの方はストレスがたまっていた。しかし、徐々に私がラトビアの生活に慣れていく感覚があった。慣れ始めたことで、自分から話しかけ、活発に行動するようになった。人に話しかけることで、この人のこういう性格が尊敬できるといった発見すると、私もそうなりたいと思って自分の中の原動力になった。1年生のうちに素敵な人たちに出会えたことで、今後の自分の人生にいい影響をもたらすだろう。
〈プログラムに参加した感想〉
日本から遠く離れた国の人たちが、独学や大学で勉強していることを知った。彼らはとても意欲的に授業に参加しており、その様子は輝いているように見えた。彼らと接していると、私ももっと貪欲に言語について勉強したいという衝動に駆られた。このプログラムに参加して、私は英語を話せるようになりたいと思っているが、アウトプットがあまりできていないことに気がついた。自分に話が振られないときは、何についてはなしているか分かるのに、自分に話が振られた途端、相手が何を言っているか分からない状況がよくあった。これは、いつも自分について問われない筆記・リスニングの勉強をしているからだと思う。口に出さないと、いざ会話になったときに話せないので、少しずつでも話していく練習が必要だということを痛感した。
〈今回の経験による今後の展望〉
ラトビアに行ったことで英語をもっと勉強して使えるようになりたいと思った。知識が足りないのもあるが、もう少し英語を話すように意識していきたい。
人見知りのため、人と仲良くなるのに時間がかかった。初めは時間がかかるかもしれないが、このように新たな出会いを求めて行動することで、次第に人見知りが緩和されていくのではないかと感じた。これからも積極的に活動していきたい。

▲ブラックヘッドハウス

▲聖ペテロ協会

▲自由の記念碑