

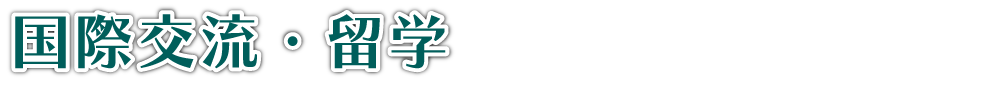


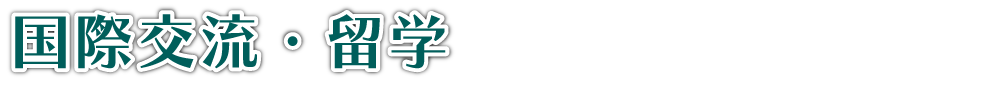
ホーム > 国際交流・留学 > 学生大使派遣プログラムについて > H30ラトビア大学 > 谷津瑞穂
派遣期間:2018年 8月27日~9月13日
日本語教室での活動内容
平日毎日夕方の授業と、月曜日・水曜日・金曜日午前中の授業を担当しました。最初の1週間はラトビア大学が夏休みのためあまり現地学生がおらず、1回の授業で多くて6~7人しかいませんでした。私たちよりも先に現地に到着していた山大の学生が、日本で使われている英語の教科書の翻訳を授業の中で行っていたので、授業の前半はそれを引き継ぎ翻訳を行いました。ただ90分翻訳をするだけではつまらないので、授業を重ねるごとに内容を工夫するようになりました。
授業の前半では引き続き日本語に訳す作業を行い、授業の後半では日本語を使ったゲームを交えて楽しみながら現地学生と一緒に勉強をしました。例えば、しりとり・折り紙を折ったり...とった定番もそうですが、「本を読んでいる男性」「海で泳いでいる子供」といった動詞+人の名詞の組み合わせのお題を出して1人の学生に前に出て絵を描いてもらい、その絵を日本語で周りの生徒が当てるというゲームをしました。また、好きな食べ物の特徴を日本語で3つ挙げてもらって、その食べ物を周りの生徒たちが当てるゲームもしました。好きな食べ物として日本料理のしゃぶしゃぶやお寿司などを挙げる人もいて、日本の食べ物を紹介するいい機会にもなり、聞いているだけではなく皆が楽しめるゲーム形式の授業を心掛けました。
2週目からは日本人の山大学生が増えたにも関わらず現地の生徒が増えず、人数集めに苦労しました。国際学生寮に滞在していたので、同じ寮にいる留学生に声を掛けて日本語クラスに呼んだり、あらゆる手段を使って人を集めました。そのため初めて日本語に触れる人も多かったので、「こんにちは」「ありがとう」「いただきます」といった基本的なあいさつの勉強から始めました。また、各自の名前に一文字ずつ漢字の候補を挙げて意味を説明し好きな漢字を選んでもらって、オリジナルの名前の漢字も作りました。マンツーマン形式で授業を行い、授業の後半は文法を教えるというよりは、少し日本語を話せる人には日本語を交えながら日本の地理や文化について紹介することに重きを置きました。会話形式でホワイトボードに日本地図を書いて地元を紹介したり、自分が旅行した時の京都・奈良・大阪のお寺や神社等の写真を見せて、「なぜ鳥居がたくさん立っているのか」「お寺と神社の違い」、お守りについてなどを日本語と英語で説明しました。
日本語を具体的に文法を通して教えることももちろんですが、初心者には特に日本により興味を持ってもらうために文化を中心に英語を日本語に替えながら授業をすることを心掛けました。
文法的な面では、「閉じる」と「閉める」の違いをどのように英語で説明するかなど、普段自分たちが何気なく使っている表現を論理的に説明するのに苦労しました。
日本語教室以外での交流活動
休日は現地の学生が電車でバルト海に連れて行ってくれたり、世界遺産の旧市街を案内してくれたりしました。
また、現地の有名なチョコレート会社のファクトリーに行って工場見学をしたり、チョコ作りをしたりラトビアの美味しいお菓子も楽しみました。
学校の近くには国立オペラ劇場があり、オペラもバレエも両方観に行きました。2回観に行っても15€でとても安かったのですが、芸術的なものにあまり触れたことがなかった私でも本当に感動しました。
旧市街の街並みは本当に綺麗で、ヨーロッパならではのカラフルな建物がたくさんありました。旧市街の真ん中にある教会の展望台に登って街を一望することができました。上から見ると旧市街と新市街の境目をはっきりと見ることができ、リガの街の歴史を感じました。
日本語クラスの生徒の中には美術館の案内のお仕事をしている人がいて、彼女が働いている美術館を案内してもらったり、サーカスや美術のエキシビションなどさまざまな現代アートのイベントに誘ってくれました。今まで日本では踏み入れたことのなかった世界をたくさん見ることができ、とても新鮮で楽しかったです。
参加目標の達成度と努力した内容
小さい頃から当たり前のように話していた日本語をいざ教えるとなると、何から教えれば良いのかが難しく、出発前に準備していたものも現地に着いてから変更した点が多々ありました。しかし、現地の学生とコミュニケーションを取っているうちに、「こんな日本の文化を紹介したら楽しそうだな」という新しいアイデアが湧くようになり、ゲームも交えるなど工夫しながら授業が出来たと思います。また、日本語クラスに参加している学生との関わりだけではなく、寮での生活の中でいろいろな国の人と話をして、外国の文化をたくさん知ることが出来たと共に、自分の知らない世界がまだまだ広がっていることにとてもワクワクしました。
このプログラムに参加した感想
このプログラムの一番の魅力は、派遣期間中の授業に出る時以外のスケジュールが縛られていないという点だと思います。もしも最初から全てのプランが決まっているプログラムだったとしたら、ラトビア人学生や世界各国からの留学生とここまで交流が出来なかったと思います。大学までの移動も含めて全て自己責任なので、自分たちでバスの定期券を買ったり、スーパーで食料を調達したり、現地学生の助けも貰いながら考えて行動することが出来たと思います。
また、日本語クラスの授業の中で最も痛感したのは、自分がいかに日本のことを知らないかということです。日本語クラスの学生の中には、何年も日本語を勉強していて、もっと深い日本の文化を知りたいという生徒もいました。「なぜ稲荷神社ではきつねを祀っているのか」「辶(しんにょう)の部分にはどのような意味があるのか」などの質問にすぐに答えることが出来ず、調べながら答えてしまいとても情けなく思いました。自分の国に対する知識の詰めが甘かったと実感した20日間でした。
今回の経験による今後の展望
今までは単に「いろんな国に行って文化の違いを肌で感じたい」という好奇心で国際関係に興味を持っていましたが、もっと大切なことがあると気付きました。外国の文化を知ることももちろん大切ですが、その前にまずは自分が生まれ育った日本の文化を学び直す必要性があると実感しました。今回のラトビアにおける滞在でも、日本人だと相手に告げると「日本はどんな国ですか?」「この日本の文化にはどのような意味があるのですか?」と何度も聞かれました。日本語クラスの学生ならば日本のことも少しは知っているのでまだ良かったのですが、国際寮で出会った日本のことをよく知らない留学生に説明するとき、日本を一言で簡単に紹介できるように考えておけば良かったと後悔しています。一緒に話した留学生は皆自分の国のことをとても楽しそうに話してくれました。彼らからとても刺激を受けることができ、私も誇りを持って日本を海外で紹介できるようにもっと勉強したいです。
▲日本語クラスでの授業風景
▲日本語クラスの授業後の一枚
▲最後の授業の日の一枚
▲現地学生と登った展望台からの一枚