

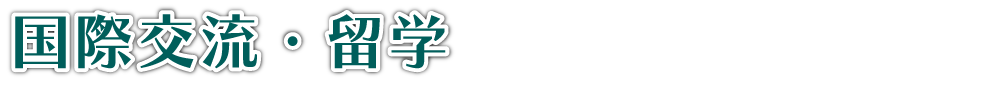


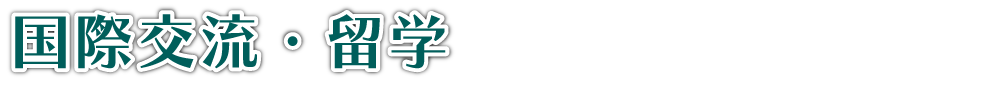
ホーム > 国際交流・留学 > 学生大使派遣プログラムについて > H30ガジャマダ大学 > 渡辺美春
派遣先大学:ガジャマダ大学(インドネシア)
派遣期間:2019/02/22~2019/03/11
この春、私は前期に続いて2回目のインドネシアを訪れました。今回は経験があるからこそわかったことや再発見したこと、感じられたことが多くありました。
@日本語教室での活動内容について
前回は教室や生徒の様子などイメージできないまま、探り探り授業をしていましたが、今回はそのような心配をせずに授業内容を考えることに集中できたのが良かったです。前回も教えたことがあった方々とも再会できて、一層深いレベルで交流することができました。以下は私が現地で実際に行っていた授業内容です。
*初・中級者向け*
今回は、殆どの方がひらがなまでは知っていたので、より実践的な授業を心がけました。簡単な挨拶程度はできる、という方には、日常会話のやりとりを1例示し(ひらがな文、必要であれば説明程度の英文)、実際に使いながら「昨日の出来事の言い方」「これからの予定の言い方」…など日本語で話せる表現の幅を増やしました。またそこから、曜日・数字・数詞・代名詞・関連する名詞、動詞…と徐々に広げていきました。
*中・上級者向け*
基本会話がわかる方には、助詞を中心に文法を教えました。ここで日本語が通じる方にはなるべく日本語を使って説明をしますが、通じない方には4単語の簡単な文をいくつも作り、その助詞をどんな場面で使うのかのイメージを伝えました。(例えば「~に」と「~へ」の違いは、「に」がplaceを強調するのに対して「へ」はヒト・モノが移動していくdirectionを強調する意味合いがある‥など)また、かなり話せる方とは、ややこしい言葉やことわざを教えたりお互いの国の文化について話したりしました。私には日本語教師の資格はないので、普遍的な文法の説明をすることよりも、ネイティブが使う感覚を伝えることを大事にしました。テキストや参考書はほとんど使わず、ホワイトボードセットとメモ・ペンのみで充分でした。
今回の活動でもう一つ大事にしていたのが、日本語とインドネシア語の相互理解です。今回の自分の目標が「派遣期間内で目一杯インドネシア語に触れる」ことだったので、単語や表現を教えながら逆にインドネシア語を教えてもらいました。授業も、私が一方的に教える受け身の形ではなく、言語の交換をすることでお互い積極的になれました。
@教室外での活動について
休日は、現地学生の皆さんが中心になって様々な観光地に連れて行ってもらいました。ジョグジャカルタはインドネシアきっての観光地なので、ボロブドゥールやプランバナン寺院群を始め沢山の遺跡があります。現在インドネシアは多くの国民がムスリムであるのに、仏教寺院やヒンドゥー教遺跡に沢山の観光客が訪れているのが不思議で面白いと思いましたが、これは異文化にも寛容な心の広い国民性の現れなのかもしれないとも考えました。遺跡以外にも動物園や海、朝市やマーケット通り、モールなど本当に色んな場所にいくことができて、毎週末が楽しみでした。
食文化にも関心があったのですが、中でも前回食べて衝撃、という洗礼を受けたのが「サンバル」という生唐辛子のソースでした。しかし今回はよっぽど慣れて、現地人と同じ辛味を楽しむことができるようになりました。日本では食べられないフルーツや食材(鳥の足先とか)には積極的に挑んで、存分に舌で楽しみました。
@参加してみて 目標達成度・感想・今後の展望
今回、私は2回同じ場所に派遣を希望するにあたって、「1回目より自分とインドネシアの繋がりを強める」という漠然とした目標がありました。そして現地で過ごしているうちに、「18日間の派遣期間中にできるだけ生のインドネシア語に触れる」という明確な目標ができました。前回の派遣の時、私たちは母国語のみで会話しているのに、現地の学生はインドネシア語(共通語)とジャワ語(現地語)、そして英語と日本語(お互いの共通言語)を駆使しているのが衝撃的で、その語学力に尊敬する反面自分の言語の乏しさに悲しくなったのです。すぐ目の前に異文化コミュニケーションの機会があるのに、言語が分からないだけで一気にその壁が大きく感じてしまう…今回は現地の友人に積極的に教えてもらいながらどんどんインドネシア語に触れていこう、と思いました。また今回の日本人メンバーの中に、インドネシア語が話せる方がいたこともとても大きかったです。話していることは同じでも、日常会話を現地人とできることは一気にその文化に溶け込んでいくように感じ、いつも感心していました。そのレベルまで及ばずとも、彼らが何を言っているのかが何となくわかるようになりたい、と思いました。
まずは、授業で教えた日本語⇒Bahasa Indonesia の流れで、単語を教えてもらいました。その都度メモブックに書きこんで、同じくインドネシア語を勉強している友人と内容を共有したりして、楽しくかつ充実した時間を過ごせました。
最初は全く上達しなかったのですが、続けていると少しだけ彼らの会話の端々がわかるようになりました。一番嬉しかったのは、インドネシア語で買い物や注文ができるようになったことです。以前はお店を選ぶのも注文も現地学生に頼りっぱなしでしたが、今回は自力で学内食堂を探してみたり、注文したりしました。その際、メニューを見て大体どんな料理なのかを予想できたり、値段を聞かれて数字を聞き取れるようになったことがとても嬉しかったです。
今回の活動を振り返って、目一杯インドネシア語に触れるという目標は達成できましたが、私は今後もインドネシア語のさらなる習得を目指したいと思うようになりました。また、それと同時にインドネシアをもっと深いレベルで知りたいと思うようになりました。前回同様かそれ以上に、現地の方々はいつも私たちの生活のサポートをしてくれ、沢山の心遣いをしてくださいました。そういった方々と知り合えたこと、時間を共に過ごせたことは本当に幸せでした。前にも増して、私はインドネシアが好きになりました。
今後の見通しとしては、まず2年次中にインドネシア以外の国・地域を訪れて、さらに異文化への見聞を広げたいです。そして自分の専攻予定である文化人類学(又は歴史学)の延長線かはたまた別のプログラムになるかわかりませんが、またインドネシアに滞在したいと思います。
最後に、このプログラムにおいてサポート、アドバイスをくださった全ての皆様に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。

▲タマンサリにて:日本人メンバーのみなさん

▲授業の様子

▲Yamagata’s Friendship Partyにて:現地学生、関係者のみなさん