ささえるひと #21
小屋寛
チェック機能で大学を支える。
「監事」が果たす重要な役割
2024.12.13

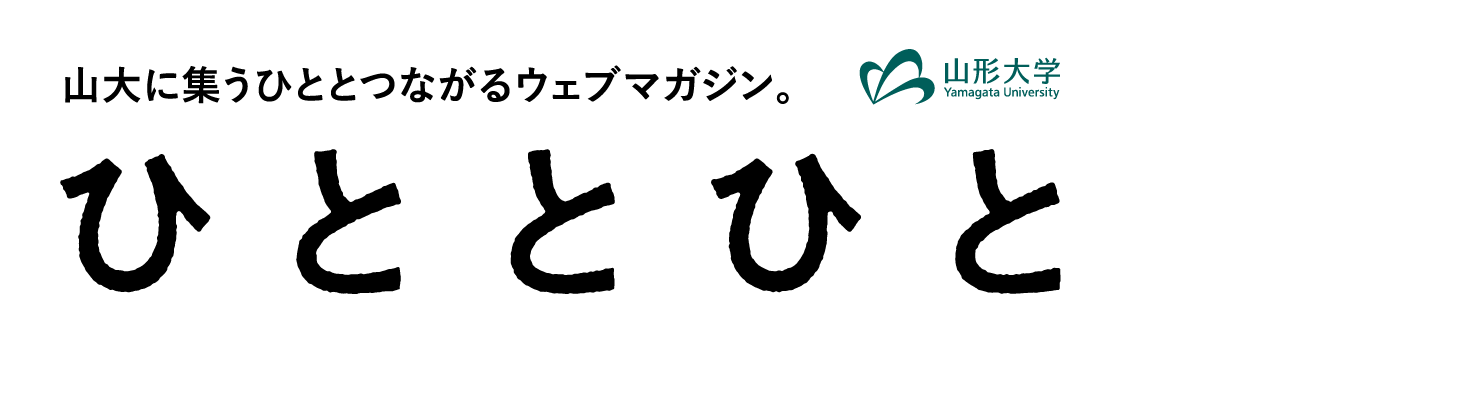
ささえるひと #21
小屋寛
2024.12.13

2024年9月に就任した小屋寛監事は、メガバンクと地方銀行で38年にわたり銀行業務に尽力してきた元銀行員。意外と知られていない「監事」の役割とともに、仕事をする上で大切にしてきたことや今後の展望、さらに「実は多趣味」という休日の過ごし方も教えていただいた。
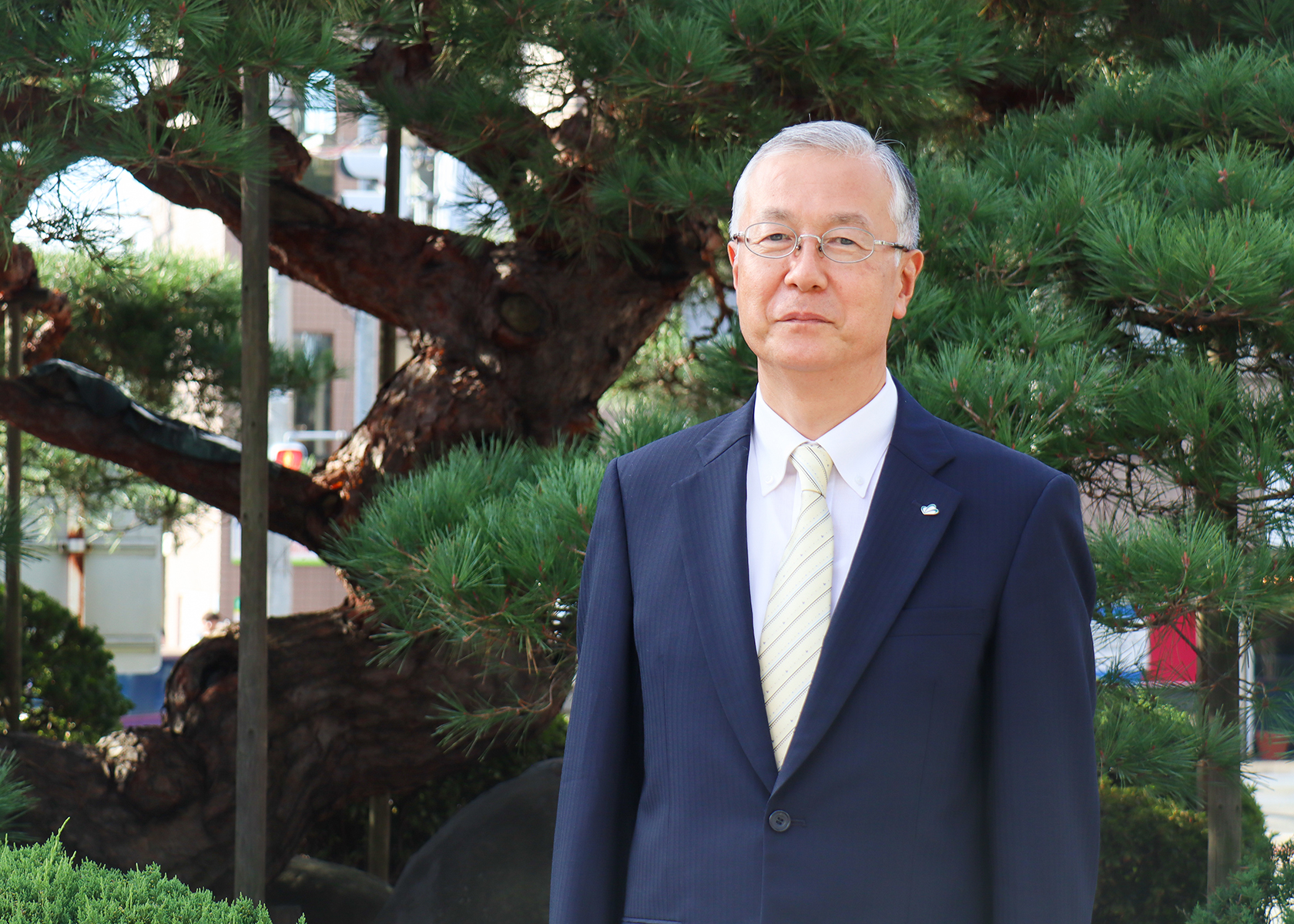
監事に就任し「大役を仰せつかった、という気持ちです。大変光栄に思うとともに、重責を感じています。これまでの経験、知識を活かし、大学や地域に貢献できれば嬉しいです」と語る。
大学の業務が多様化・複雑化する中で、法人が管理運営を適正に行い、説明責任と透明性を確保していくために重要な役割を担っているのが「監事」。
小屋寛監事は、その役職について「国立大学法人の適正かつ効率的な運営を図るために、法人の業務、会計について監査する。要はチェック機能です」と説明する。「具体的には、書面を出してもらったり、実地としてその場に行ったり、ヒアリングしたりして“すべきこと”が正しく無駄なく効率的に行われているかどうか確認します」
重要な会議に実際に出席し意見を述べることも、役職員に対して資料の提出や説明、報告を求めることもできるが、監事が業務執行に直接携わることはできない。
自身がその役割を果たすことで「内部でも、そして外部からも大学を守ることができる」と考えるという小屋監事。
「『あの監事に突っ込まれないようにきちんと記録を残しておこう』といった、いい意味での“牽制機能”を内部で働かせることができれば、外部に対しても適正な管理運営を示せるようになります」と強調。「最も困るのは、都合の悪いことを隠されてしまうこと。“なあなあ”はいけませんが、どんなことでも言える関係性が大切。監査の機会に加え、各種会議等に参加させていただいて公私両面において接する時間を重ね、相互理解を深めていくことが仕事に良い影響を与え、大学を良くすることにも繋がると考えます。ご協力、お付き合いをお願いします」と呼びかける。
「財務分析を通して本学の財務状況を正しく理解し、内部統制システムの機能発揮に取り組むのはもちろん、活用可能な事例など他大学の状況も学びながら本学の改善に取り組みたいと思います」と力を込める。

かつて学外から見ていた山形大学には「『産業界とは時間の流れが違い、中長期的なスパンであくせくしていない教育研究の拠点』というイメージがありました」という小屋監事。「『研究室で文献や実験器具を相手に時間を費やしている』と勝手に想像していましたが、いざ学内に入っていろいろな方々とお話し、実際に見ると、思っていた以上に皆さん非常に多忙で、フィールドワークも多いことが分かりました」と打ち明ける。
学生時代に読んだ企業小説をきっかけに興味を持った住友銀行(現三井住友銀行)に新卒入社。その後、生まれ育った地元にUターン、山形銀行で実績を重ねた小屋監事。
その経験から「地方大学と、地方銀行は置かれている環境や状況、期待役割の変化がよく似ている」と感じたといい「例えば大学は調査研究結果を含めた知恵・知識、ノウハウといった情報提供と、直接的な人材育成・人材供給が役割。実は銀行にも資金や知識、ノウハウといった情報提供、出向などの形で一般企業に人材を供給するような役割があります」と指摘する。
「かつて銀行は最も遅い船に速度を合わせる“護送船団方式”的な経営を行っていましたが、自主独立・自由化が進んだ現在は従来できなかった保険や投資信託のような業務も解禁され、自ら考えて自ら稼がなければならなくなりました。昔は『お金を貸していればよかった』のが、今は経営改善支援、営業支援、マッチングといった、さまざまな地域貢献も求められています。同様に大学も、交付金などを減らされて自ら稼がなければならなくなり、従来どちらかというと教育研究重視だったのが、今では社会貢献、地域創生と期待される役割も変化してきています」。

「銀行員時代、上司や先輩に教わり、実際に仕事や生活の中で『その通りだな』と思ったことを信条にしてきた」という小屋監事。例えば、上司から学んだ旧住友銀行の堀田庄三元頭取の言葉が「おいあくま(おこるな/いばるな/あせるな/くさるな/まけるな)」。新しく物事をやるときのセオリー「守破離」も心がけてきたことの一つだ。
「かつて私が学生だった頃、特定の大学からしか採用しない企業もあって、大学は“勝ち組”となるために行くところでした」と振り返る小屋監事。
「今は“価値組”となるために行くところ。社会構造の変化に伴う課題を解決する知識、ノウハウを身につけるために行くところへと、大学の役割は変化していると感じます」と語る。
中でも地方大学の使命として「高等教育機会の平等」「リベラルアーツ」の提供を重視する。
「一つの学問で解決できない社会課題も、いろいろな学問を融合させることで解決できます。人間の悩みを解決するために、哲学的な教養も重要です。地域における芸術や文化、人文系の基盤教育、リベラルアーツ提供の場という意味でも山形大学の存在価値は大きい。大切にしていかなくてはいけないと思います」。
さらに山形大学発展の鍵として、大学が掲げる将来ビジョンにも着目。「銀行や企業にも株主や取引先、地域など多くのステークホルダーがいますが、大学のステークホルダーは自治体や市民、民間企業、地域産業、小中学校・高校、NPO…と多岐にわたります。本学の『つなぐちから。』という将来ビジョンは、とてもよくできている。税金や公的な資金、国費が投入されている性質から考えても、国立大学法人である山形大学の受益者は、学生だけでなく、社会全般である必要があります」と指摘する。
ステークホルダーのうち、大学に向けた鍵の一つとして挙げるのが「卒業生」とのつながりだ。
「首都圏や大都市圏の大学なら学費を上げても、おそらく学生は集まるでしょう。しかし地方大学の学費が高くなれば、地元の人であってもより学費の安い別の大学を選んでしまう。人口減少に直面する今、地方大学には地域の衰退をくい止めて活性化に貢献していく、首都圏の大学以上の“プラスアルファ”が求められています。そうした意味で、卒業生に地元に残って就職し活躍してもらうことが非常に重要です。大学は卒業生との関わりを強化していくことも大切ではないかなと思います」。

趣味の一つが料理。「1回作っておいて温めて食べられるようなカレー、シチュー、ポトフ、おでんといったメニューを作ります」。他にも家庭菜園や読書、音楽・落語・講談・テレビ番組鑑賞、スポーツ観戦、ゴルフ練習…と「時間が足りない」と笑う。散歩やウォーキング、ジョギングも好きで、自宅から大学まで毎日45分かけて徒歩で通うのが日課。「歩いているときは語学アプリを聞いています。通勤だけで1万歩以上。脇道に入って立派なお寺などを見つけることもあります」と話す。
つづきを読む

こや ひろし●山形市出身。大学卒業後、株式会社住友銀行(現三井住友銀行)で8年間銀行業務を経験。1994年地元に戻り、山形銀行に入行。本部6部と営業店5店で経営企画、リスク管理、コンプライアンス統括などを中心に営業企画・推進管理、有価証券運用などに従事、役員(取締役・常務取締役)を経て、2024年9月より現職。
※内容や所属等は2024年11月当時のものです。