まなぶひと #56
諸田ほのか&佐藤千尋
舟形町の魅力を発信する学生食堂の
定食を企画。
授業が地域の課題を考えるきっかけに。
2025.05.15
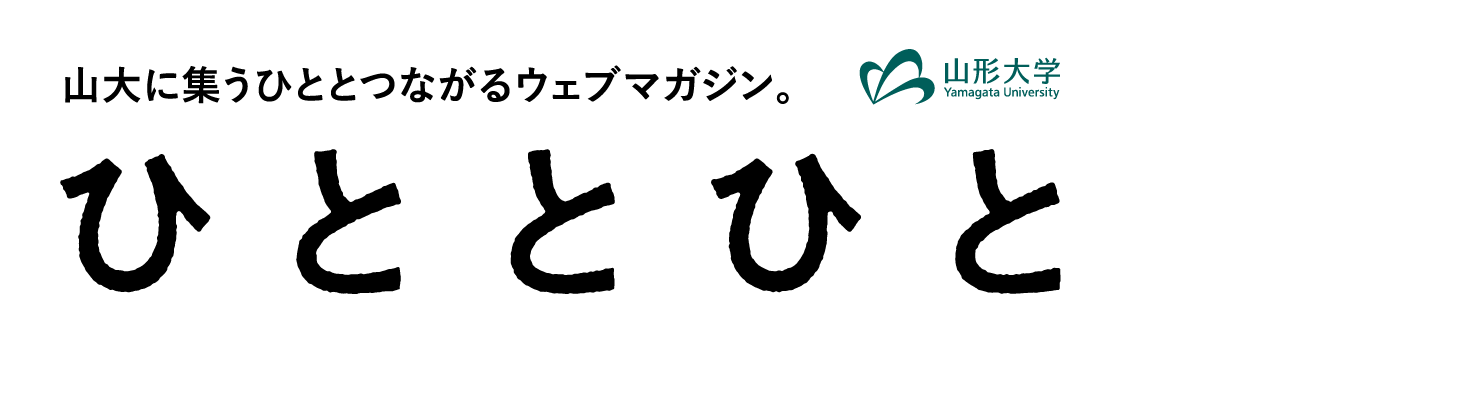
まなぶひと #56
諸田ほのか&佐藤千尋
2025.05.15
小白川キャンパスにある山形大学厚生会館食堂に2025年1月、山形県最上郡舟形町産の野菜を使った3日間限定の定食が登場した。企画したのは、学生有志による「舟形まんぷくプロジェクト」。学部・学科・専攻の枠を超え山形大学の学生全員が受講する基盤共通科目「山形から考える」の授業にある「フィールドラーニング─共生の森もがみ」で、同町について学んだことが定食発案のきっかけだったという。リーダーの諸田ほのかさんと、メンバーの佐藤千尋さんに活動の経緯や思いを聞いた。
プロジェクトリーダーの諸田ほのかさん(写真右)と、メンバーの佐藤千尋さん
「舟形まんぷくプロジェクト」は、山形県最上郡舟形町産の食材を使った定食の提供を通して、舟形町の魅力や地域課題に関心をもってもらおうと、学生有志が発案。山形大学や地域との関わりを深める学生主体の活動を大学が支援する「学生チャレンジプロジェクト」を活用し、山形大学厚生会館食堂の料理長に相談しながら、舟形町産の白菜やキャベツなどを使った「中華丼」「かき揚げ丼」「あんかけ焼きそば」の3種類の定食を企画した。
提供に当たっては、舟形町堀内地区の「堀内ファーム」の協力を得て、大根の味噌汁をセットにした定食スタイルで1食400円から500円までのリーズナブルな料金を実現。
多くの食堂利用者に大好評を博し、プロジェクトに参加した佐藤さんは、「材料の野菜が足りなくなったり、提供時間に制限をかけたりしなければならないくらいの反響。たくさんの学生が美味しそうに食べてくれました。過去に同じプロジェクトを立ち上げた先輩も食べに来て声をかけてくれて『やって良かった』と思いました」と振り返る。

告知ポスターや野菜の産地である舟形町堀内地区を紹介するチラシも学生たちが手作り。「舟形町の魅力についてみんなに知ってもらった上で野菜を食べることで、いつもとちょっと違ったおいしさを感じてもらえるのではないかと考えました」と諸田さんは説明する。 (※アンケートはすでに終了しています)
プロジェクト立ち上げのきっかけになったのは、山形大学の基盤共通科目「山形から考える」。講義、セミナー、フィールドワークといった多様なスタイルで山形県の「地域」そのものを学ぶ科目で、他県出身の学生が山形県に興味を持ち、県内出身者が故郷の新たな魅力に触れる好機にもなっている。
その中でも「フィールドラーニング─共生の森もがみ」 は、最上広域圏8市町村の文化や歴史、自然、環境はもちろん実際に足を運び、フィールドワークの入門編として山形大学が独自に設計した「フィールドラーニング」の手法で、過疎化や少子高齢化といった現代日本が直面する地域の諸問題を現地の人たちとともに学ぶ授業だ。
諸田さんら舟形町のプログラムを選んだ学生たちのグループは、事前学習を行った後、1回目のフィールドラーニングで地域が抱える課題を探り、中間学習を経て2回目のフィールドラーニングで理解を深めて活動報告会で成果を発表した。
活動報告会の準備の過程で町への貢献策として、メンバーが発案したのが「舟形野菜の定期便」と「学生食堂の定食提供」の2案だった。「大変良くしていただいた舟形町の役に少しでも立ちたいと考えました」と諸田さん。
野菜の定期便は学生だけでは実現が難しかったことから、学生食堂の定食提供の案を企画書にまとめ、大学の「学生チャレンジプロジェクト」の採択を経て、グループの有志による活動が始まった。
集まった学生有志8人の所属は、それぞれ理学部、医学部、工学部、農学部とさまざま。互いのスケジュール調整には苦労したという。「全員の日程が合わず、ようやく集まれても 2、3 人がやっと。『スプレッドシート』 を使ってみたり LINE の投票式にしてみたり、試行錯誤しました」と諸田さん。舟形町の生産者、役場担当者、山形大学厚生会館食堂関係者への連絡や打ち合わせにも苦戦し、「外部の方と連絡を取ること自体が初めてで、失礼もあったと思いますが、こうしたプロジェクトを進める中での学びは大きかった。いい経験ができたと思います」と話す。
定食を食べた学生には、アンケートを依頼し、舟形町の認知度などについてデータの集計・分析を行ったが想定外の事態が発生。 山大生たちの舟形町の認知度がメンバーの予想よりはるかに高かったのだという。
「舟形町を広めるためのプロジェクトでしたが、山形出身の学生はもともと皆、知っていた。県外出身でも、サークルの合宿などで舟形町に行く学生は多く、2年生以上の知名度は高かった。私たちが県外出身の 1 年生ばかりだったから、それを知らなかった」と2人は苦笑する。

チラシを配って定食の提供をPRし、アンケート協力を呼びかける「舟形まんぷくプロジェクト」のメンバーたち
プロジェクトの活動の中で諸田さん、佐藤さんが「特に印象に残っている」と口をそろえるのが農業ボランティアの活動だった。定食の提供に先駆け「舟形町についてより深く学ぼう」と、再び舟形町を訪ね、芋掘りなどの農作業を経験した。
訪れたのは秋。授業のフィールドラーニングで舟形町を訪れた初夏とは違った発見があったという。

撤収作業などの農業ボランティアを経験
「夏以外の季節にも、これほど多くの作業があること、他の農家と時期をずらすなど栽培や出荷の複雑な“戦略”があることなどを初めて知りました。舟形町は地図上で見るとそれほど大きくないし、人口も多いようには感じませんでしたが、産直施設に行くと、見たことのないような種類の野菜が多い。この町だけで、これだけたくさんの野菜が育てられている。私たちが食べているものがこうやって育てられていることを初めて実感しました」と諸田さん。「地域の 1 番の問題は高齢化と人手不足。今までもなんとなく知ってはいましたが、授業と農業ボランティアがあったからこそ深く学ぶことができました」と力を込める。
実家が兼業農家で、農学部で学ぶ佐藤さんにとっても大きな刺激になったようだ。
「自給率が低い日本は、ただでさえ海外輸入に頼っている状態。人手不足、農業の継手がいなくなっていることで、将来の食がどうなるのか。機械を導入するにしても、購入費も管理費も維持費もかかる。人を増やすにも、どこからか連れてくれば、別のどこかが減る。どうすればいいのだろう、と悩んでしまいました。本学の農学部では、農業についてより専門的に学ぶことができるので、これからいろいろな知識をつけていきたいと改めて思っています」

舟形町で昼食を楽しむプロジェクトのメンバーたち
つづきを読む
もろた ほのか●理学部理学科2年生。愛知県出身。宇宙分野への関心から山形大学に入学。「高校時代はほぼ座学だけだったので、実習できることに惹かれました」と、フィールドラーニング─共生の森もがみの授業を選択。「キュウリの栽培準備を体験し、カエルやヤモリなどの生き物も見られて楽しかったです」と振り返る。サークル活動では、ジャグリングや「魚突き」にも挑戦中。
さとう ちひろ●農学部食料環境学科2年生。新潟県出身。実家が兼業農家で、「農業について詳しく知りたくて」山形大学に入学。フィールドラーニング─共生の森もがみの授業を履修し、初めて最上地域に足を運び「地元と似た雰囲気で『懐かしい』と感じました。収穫量を増やす工夫や人手のやりくりなど実家とは違う、大規模な農業経営に驚きました」。と振り返る。サークル活動では、文芸部、美術部に所属する。
※内容や所属等は2025年4月当時のものです。